
マイローカルコンビニ
はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。
「ひどい セブンイレブン 底上げ」と検索されたあなたは、セブンイレブンの商品に対する不信感や疑問をお持ちではないでしょうか。
SNSや匿名掲示板のなんJなどでは、長年にわたり「上げ底」と疑われる容器に関する指摘が相次ぎ、消費者の客離れを招く理由ではないかと噂されています。
他社コンビニとの底上げ 比較画像や、一連の上げ底問題に対する消費者庁の動向、さらには新体制になって「底上げ やめた」という噂の真相まで、様々な情報が錯綜している状態です。
中には「日本一クレームが多いセブンイレブンはどこですか?」や「セブンイレブンの離職率は?」といった、底上げ問題をきっかけに、企業の体質そのものにまで疑問を持つ声も見受けられます。
この記事では、そうした「ひどい」と言われる事例のまとめや、底上げのまとめ情報を含め、なぜセブンイレブンの「底上げ」がこれほどまでに長期間、そして深刻に問題視されるのか、その背景と現状を多角的に解説していきます。
記事のポイント
- セブンイレブンの底上げが問題視される理由
- SNSやネットで「ひどい」と言われた具体的事例
- 他社コンビニとの比較とセブンイレブンの見解
- 新体制で「底上げをやめた」のか、最新の動向
ひどい?セブンイレブンの底上げ問題の経緯
- 業績悪化と客離れの現状
- 容器の形状変更、その理由とは
- SNSやなんJでの厳しい意見
- 炎上した「ひどい」事例まとめ
- 上げ底と消費者庁の関連性
業績悪化と客離れの現状

マイローカルコンビニ
日本のコンビニ業界は、長らくセブンイレブンが圧倒的なシェアと利益を誇る「一強」状態が続いていました。しかし、その牙城が揺らぎ始めています。
2024年8月に発表された中間連結決済では、ローソンとファミリーマートが前年同期比で増益を達成したのに対し、セブンイレブン(セブン&アイ・ホールディングス)だけが減益という衝撃的な結果が報じられました。
もちろん、この減益の主な要因は北米事業(スピードウェイなど)の不振が大きいとされています。ただ、国内のコンビニ事業に目を向けても、決して安泰とは言えません。
例えば、2024年5月の既存店客数が前年比でセブンイレブンのみ(2.3%減)減少するなど、国内での「セブン離れ」を指摘する声も少なくないのです。
この厳しい現状については、2024年5月に就任したセブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋・新社長も認めています。
阿久津社長は、この客数減少の背景に、消費者からの「好意度」に大きな課題があると考えており、ブランドイメージの改革が急務であると訴えています。
消費者の不満が業績に与える影響
もちろん、業績不振の理由が「底上げ」問題だけにあると断定することはできません。
しかし、SNS上で10年近くにわたり蓄積されてきた「またセブンか」「消費者を騙している」といった「騙された感」が、消費者のセブンイレブンに対するブランドイメージ(好意度)を確実に低下させ、「セブン離れ」の一因となっている可能性は十分に考えられます。
容器の形状変更、その理由とは

マイローカルコンビニ
では、なぜセブンイレブンはこれほどまでに「底上げ」と疑われるような容器を使用し続けてきたのでしょうか。
この根深い問題について、永松文彦前社長(当時)がメディアの取材に対し、その理由を説明しています。
セブンイレブン側の主な見解(言い分)は、大きく分けて以下の2点です。
- 環境配慮(プラスチック削減)
昨今の環境問題への対応として、容器に使用するプラスチックの絶対量を削減し、素材を薄くする「薄肉化」を進めている。
その際、ペラペラになってしまう容器の強度を保つための設計として、底面に凹凸や傾斜(リブ構造)をつける必要があった、というものです。 - レンジ加熱の効率化
弁当などを電子レンジで温める際に、熱が伝わりにくい中心部まで均一にマイクロ波が通り、熱が伝わりやすい形状を追求した結果、底が盛り上がった形状になっている、という主張です。
永松前社長は「(消費者を騙すような)アコギなことはできない」と、意図的なかさ増しを強く否定しました。
しかし、この発言に対し、SNSでは「それならそうと容器に明記すべきだ」「理屈はわかっても、体感として量が少ないのは事実」「その工夫で減った原価分を還元しているのか」といった反発の声がさらに多く上がり、消費者の納得を得られたとは言い難い結果となりました。
SNSやなんJでの厳しい意見

マイローカルコンビニ
セブンイレブンに対する「底上げ」の指摘は、ここ1~2年で急に始まったことではありません。
実際には、10年ほど前からSNSの普及と時を同じくして、匿名掲示板「なんJ」やX(旧Twitter)などでたびたび話題になってきました。
特に槍玉に上がったのが、「スタミナ炭火焼肉弁当」や「釜飯」といった商品です。
これらは外側の立派な容器と、内側のご飯や具材が入っている容器が分離する「二重底」構造になっていたり、容器の底が異常なほどに盛り上がっていたりすることで、「見た目のボリューム感と実際の内容量に差がありすぎる」と厳しく指摘されました。
「サイレントケチ盛り」という厳しい指摘
SNS上では、こうした手法を「サイレントケチ盛り」と呼ぶ声もあります。
これは、価格を維持したまま内容量をこっそり減らす「ステルス値上げ」の一種と捉えられています。
「加熱効率の工夫」として開発されたパッケージが、消費者側には「客にバレないように量を減らす不誠実な商売」と映ってしまったのです。
しかも、消費者の不信感を招いたのは、この「底上げ」問題だけではありません。
- 陳列時に見える部分(断面)にだけ具材を寄せた「はりぼてサンドイッチ」(サンドイッチがひどいという噂の発端の一つ)
- 北海道地区で販売され、実際には海苔が巻かれていないのにパッケージに海苔が印刷されていた「海苔印刷おにぎり」
- 中身が空洞だったとされる「空洞塩むすび」(こうした事象から「セブンのおにぎりはまずくなった」とまで言われる事態に)
- 果肉がたっぷり入っているように見せかけるため、容器に果肉風の塗装を施した「練乳いちごミルク」
これらの事例が(一部はイレギュラーや誤解も含むものの)同時多発的にSNSで拡散され、積み重なった結果、「セブンイレブンは消費者を騙そうとしている」というネガティブなイメージが強固に定着してしまったと考えられます。
炎上した「ひどい」事例まとめ

マイローカルコンビニ
セブンイレブンが「ひどい」と批判された主な事例を、改めて時系列や分類で整理します。
これらは「底上げ」問題だけでなく、消費者に「騙された感」を与えた複数の事象を含んでいます。
| 事象の分類 | 具体的な事例(商品名など) | 指摘された内容 |
|---|---|---|
| 容器の底上げ | ・スタミナ炭火焼肉弁当 ・各種パスタ商品 ・釜飯風弁当 | ・容器が二重底(セパレート構造)になっている。 ・底の中心が極端に盛り上がっており、見た目より内容量が少ない。 |
| パッケージ(見た目) | ・練乳いちごミルク ・sonnaバナナミルク ・炭火焼き鳥おむすび(北海道) | ・果肉やピューレが入っているように見える塗装(プリント)が施されていた。 ・海苔が巻かれているように見える印刷だった。 |
| 内容物(ハリボテ) | ・一部のサンドイッチ ・ツナサンド | ・断面(見える部分)にのみ具材が偏っており、中身が少なかった。 ・ツナが入っていないという報告が相次いだ(※イレギュラーの可能性も指摘あり)。 |
| 実質値上げ | ・いなり寿司(3個→2個) ・塩むすび | ・リニューアルで個数が減った(ステルス値上げ)。 ・おむすびの内部が空洞になっているという指摘が相次いだ。 |
重要なのは、これらの事象が消費者に「またセブンか」と認識された点です。
一つの問題が解決する前に次の問題がSNSで発覚する、という連鎖が、「セブン=不誠実」というブランドイメージを決定づける要因となったのです。
上げ底と消費者庁の関連性

マイローカルコンビニ
SNSで「上げ底」が炎上するたび、必ずと言っていいほど「景品表示法の優良誤認にあたるのではないか?」という指摘がなされます。
景品表示法における「優良誤認」とは、簡単に言えば、商品やサービスの内容が、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤解させるような表示のことです。(参照:消費者庁「景品表示法」)
この問題に関して、セブンイレブンが「底上げ容器」や「パッケージ印刷」を理由に消費者庁から直接、景品表示法違反として行政処分(措置命令など)を受けたという公式な情報は見当たりません。
セブンイレブン側も、前述の通りあくまで「加熱効率」や「強度保持」が目的であり、かさ増し(量を誤認させる)意図はない、と説明しています。
しかし、法律違反に該当するかどうかと、消費者がどう感じるかは別の問題です。
消費者庁が実施した「物価モニター調査」では、消費者の多くが「実質値上げ(ステルス値上げ)」に対して極めてネガティブな印象を持っていることが示されています。
具体的には、82.2%が「3年前と比較して実質値上げが増えたと感じる」と回答しており、消費者の目は非常に厳しくなっているのです。
法的な問題と、信頼の問題
法的に「セーフ」であったとしても、消費者が「裏切られた」「騙された」と感じた時点で、ブランドイメージは大きく毀損されます。セブンイレブンが直面しているのは、法的な問題以上に、失われた「信頼」の問題であると言えます。
ひどいセブンイレブンの底上げ疑惑への反論と他社比較
- 他社コンビニとの底上げ比較
- 新社長は「底上げ やめた」のか?
- セブンの底上げ まとめと現状
- 日本一クレームが多いセブンイレブンはどこですか?
- セブンイレブンの離職率は?
他社コンビニとの底上げ比較

マイローカルコンビニ
セブンイレブンの「底上げ」が際立って批判される一方で、「他社(ローソン、ファミリーマート)だってやっているのでは?」という疑問も生じます。
実際のところ、他社の状況はどうなのでしょうか。
過去にネット上で複数のユーザーによって実施されたサンドイッチの比較実験では、非常に興味深い結果が報告されています。
もちろん、人気のたまごサンドのように味で高い評価を得ている商品もありますが、ここでは量や見た目について検証されています。
ある実験では、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップのミックスサンドを比較したところ、以下のような傾向が見られました。
- 重量:セブンイレブンが最も軽かった(117g)。(※1位はローソン・ファミマの136g)
- 中身:セブンは「軽い」という第一印象の不安があったものの、中身は意外とみっちり入っており、「詐欺感はなかった」と評価されています。
- 味:「ハムレタスは(シャキシャキ感があり)ダントツで美味しい」「味の満足度はめちゃ高かった」と、味のクオリティに関しては高く評価されました。
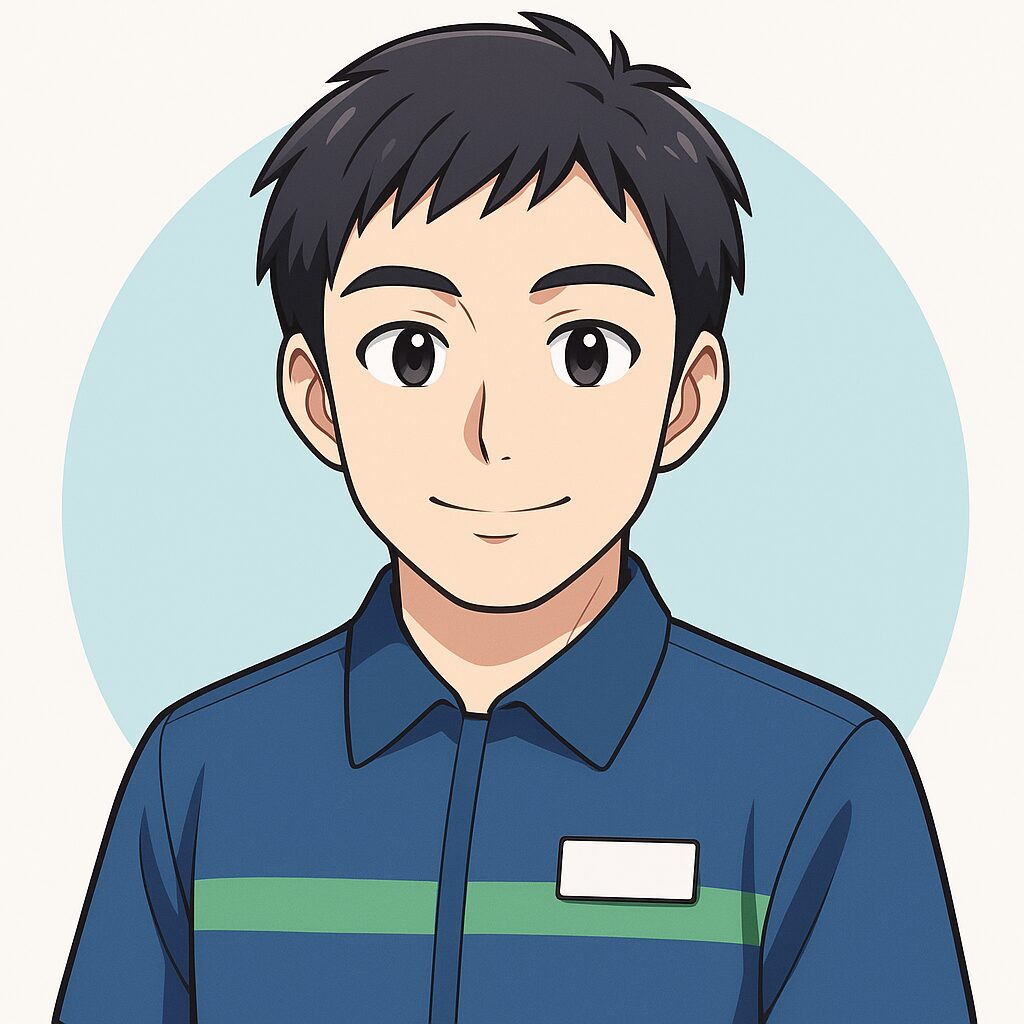
「セブンイレブンだけが意図的にハリボテサンドイッチをレギュラー商品にしているわけではない」可能性が示唆される一方で、「重量が他社より軽い」という事実は、消費者が「量が少ない」「割高だ」と感じる客観的な一因となっているかもしれません。
他社の増量キャンペーン
セブンイレブンが「底上げ」や「ステルス値上げ」で消費者の厳しい視線にさらされる一方、ローソンやファミリーマートは「増量キャンペーン」で消費者の心を掴みました。
特にファミリーマートが2021年から(創立40周年を記念して)始めた「お値段そのまま40%増量」は、大きな人気を博しました。
ファミチキやサンドイッチ、弁当などが文字通りボリューム満点であるとSNSでも大きな話題となりました。
ローソンも「盛りすぎ!チャレンジ」といった同様のキャンペーンを定期的に実施し、売上を伸ばしています。セブンイレブンもカレーフェスのような独自の人気企画を行っていますが、消費者の「量」に対する不満と直接向き合う他社の戦略が際立つ結果となりました。
対極として称賛された「キッチンDIVE」
セブンイレブンの「上げ底」問題が炎上するたびに、SNSでは「『キッチンDIVE』を見習え」という声とともに、規格外のデカ盛り弁当の画像が拡散されました。
「キッチンDIVE」は東京都江東区などを中心に展開する弁当店で、「1キロ弁当」や「1キロおにぎり」といった、採算を度外視したかのようなデカ盛り商品を販売しています。
同店の伊藤慶代表は、メディアの取材に対し「(当初の格安弁当から)デカ盛りにしたことで逆に客単価が上がり、コロナ禍でも売り上げは安定的だった」と語っています。
セブンイレブンの戦略とはまさに対極にあるビジネスモデルと言えます。
新社長は「底上げ やめた」のか?

マイローカルコンビニ
長年にわたる消費者の不信感が募る中、2024年5月にセブン‐イレブン・ジャパンの新社長に阿久津知洋氏が就任しました。
そして阿久津新社長は、このデリケートな「底上げ」問題について、メディアのインタビューで驚くべき発言をしたのです。
それは、「正直、“上げ底弁当”といわれるように、問題はあったと思っています」という、これまでの問題を真正面から率直に認めるものでした。
これは、従来の「(加熱効率や強度のための)工夫である」という企業側の論理を繰り返すのではなく、消費者から「問題だ」と指摘されてきた事実そのものを受け止めた発言であり、非常に画期的なことでした。
新社長の認識と具体的な対策
阿久津社長は、これらの問題がお客様の信頼を裏切り、現在の「好意度」の低下に直結していると深く分析。
た、問題を認識していながら、それを消費者に向けて適切に発信できなかったことにも課題があったと述べました。
具体的な対策として、「商品総点検」というプロジェクトをすでに立ち上げ、企画側の社員ではなく、日常的に店舗でお客様と接しているオペレーション(店舗運営)側の社員が「お客様からどう見えるか」という厳しい視点で、既存の全商品を精査したと明かしています。
今後は「優等生だけど面白くない」という現状の評価を覆し、「優等生だけど面白いやつ」を目指すとして、新しさや驚きのある商品開発を進める方針です。
この新社長の率直な姿勢と具体的な取り組みは、「セブンイレブンは変わるかもしれない」「底上げをやめるのではないか」という期待を消費者に抱かせるものとなっています。
セブンの底上げ まとめと現状

マイローカルコンビニ
セブンイレブンの「底上げ」問題は、単なる容器の形状の問題ではなく、企業と消費者とのコミュニケーションの失敗であったと結論付けられます。
前社長(永松氏)の主張: 「上げ底」の事実は認めるが、その理由は「レンジ加熱効率」と「強度維持」のため。
消費者を騙す「アコギなこと」ではない、という企業の論理を優先した説明。
新社長(阿久津氏)の認識: 「問題はあった」と率直に認め、それが客の信頼を裏切り「好意度低下」につながったと分析。
「商品総点検」による具体的な改善に着手したと発表。
両者の発言からは、消費者との向き合い方に明らかな変化が見て取れます。
なぜ「底上げ」戦略が生まれたのか?(分析)
「キッチンDIVE」の伊藤代表は、セブンイレブンの戦略について的を射た分析をしています。
「(最大手として)価格と量のちょうどいいところを取り、品質や見栄えを優先している」「お弁当だけで満腹にさせず、お惣菜やペットボトルコーヒー、お菓子などの『ついで買い』をしてもらったほうが客単価が取れるのではないか」という指摘です。
また、日本の消費者は「同容量で値上げ」を極端に嫌う傾向があるとされます。
そのため、企業側は「価格そのままで容量減(ステルス値上げ)」という、後で発覚したときに非難されやすい選択肢を選ばざるを得なかった、というデフレスパイラルの中で生まれたジレンマも背景にあると考えられます。
日本一クレームが多いセブンイレブンはどこですか?

マイローカルコンビニ
「日本一クレームが多いセブンイレブンはどこですか?」という検索キーワードは、おそらく特定の1店舗を探しているというよりも、「セブンイレブン全体への不満の表れ」や「どの店舗でも問題が起きているのではないか?」という漠然とした疑問や不安の表れと考えられます。
当然ながら、特定の1店舗が「日本一クレームが多い」と公式に認定された事実はありません。
セブンイレブンは、日本国内に21,000店舗以上(2024年時点)を展開する最大のコンビニチェーンです。(参照:セブン‐イレブン・ジャパン 企業情報)
店舗数と利用者が他社の追随を許さないほど圧倒的に多いため、商品の納品時間なども含め、オペレーションに関する様々な意見(クレームやSNSでの指摘も)が集まりやすく、目立ってしまうというのが実情でしょう。
「底上げ」問題がこれほど大きな社会的話題となったのも、良くも悪くも日本で最も利用され、注目されているコンビニチェーンであることの裏返しと言えます。
セブンイレブンの離職率は?

マイローカルコンビニ
「底上げ」のような消費者の信頼を損ねる行為が続くと、「企業体質そのものに問題があるのではないか?」「社員が定着しないブラックな環境なのでは?」という疑問から、「セブンイレブンの離職率は?」と気にされる方もいるようです。
セブン&アイ・ホールディングスが公開している「統合報告書」や「ESGデータブック」によると、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(本部社員)の単体の離職率は4.5%(2022年度実績)とされています。 (参照:セブン&アイ・ホールディングス IRライブラリ)
この数値の解釈についての注意点
この4.5%という数値は、日本の企業全体の平均離職率と比較しても、特に高いとは言えません。
むしろ、大企業としては標準的な範囲内でしょう。
ただし、この数値の解釈には注意が必要です。
これはあくまで「本部社員」の数値です。
消費者が日常的にイメージする「セブンイレブン」には、全国のフランチャイズ加盟店の店舗オーナーや、そこで働くアルバイト・パートスタッフも含まれます。
フランチャイズ経営の厳しさや、店舗スタッフの高い流動性といった問題は別途存在します。
「離職率4.5%」という数字だけを見て「問題ない」と判断するのは早計かもしれません。
よくある質問
Q:なぜセブンイレブンは「底上げ」と呼ばれる容器を使っているのですか?
A:セブンイレブン側の説明では、「プラスチック使用量削減による容器の強度保持」と「電子レンジで均一に温めるため」の工夫とされています。しかし、消費者からの批判を受け、2024年に就任した阿久津新社長は「問題はあった」と認め、全商品の見直しを進めています。
Q:「底上げ」以外にも「ひどい」と言われる事例はあったのですか?
A:はい。容器の底上げ以外にも、見える部分にだけ具材を寄せた「ハリボテサンドイッチ」、海苔が巻かれているように見える「海苔印刷おにぎり」、果肉が入っているように見せた「容器塗装ドリンク」などがSNSで次々と炎上し、消費者の不信感を高める原因となりました。
Q:セブンイレブンだけが「底上げ」をしているのですか? 他社との比較は?
A:セブンイレブンが特に厳しく批判されていますが、他社も加熱効率などのために容器の工夫はしています。しかし、ローソンやファミリーマートは「お値段そのまま40%増量」や「盛りすぎチャレンジ」といった逆の戦略で支持を集め、セブンイレブンの「量を減らしている」というイメージと対照的な結果となりました。
Q:「底上げ」問題は消費者庁から指導を受けましたか?
A:SNSでは景品表示法の「優良誤認」にあたるのではとたびたび指摘されましたが、2024年現在、セブンイレブンがこの「底上げ」問題で消費者庁から直接、行政処分や措置命令を受けたという公式な情報は見当たりません。法的な問題とは別に、消費者の「信頼」を失ったことが最大の問題点とされています。
ひどいセブンイレブン底上げ問題の今後
この記事では、セブンイレブンの「ひどい」と言われる「底上げ」問題について、その経緯や背景、他社との比較、そして新社長の真摯な見解までを詳しく解説しました。
セブンイレブンは今、阿久津新社長の下で「失われた信頼」を回復するための正念場を迎えています。
単なる商品改善だけでなく、過去の「問題」を率直に認め、消費者に誠実に向き合う姿勢を示し続けられるかどうかが問われています。
最後に、本記事の要点をリストでまとめます。
- セブンイレブンは2024年の中間決算で大手3社で唯一減益となった
- 業績悪化の背景に国内の「客離れ」を指摘する声がある
- SNSやなんJでは10年以上前から「底上げ」容器が批判されていた
- 「底上げ」以外にも「ハリボテ」や「パッケージ詐欺」疑惑が炎上
- 前社長は底上げの理由を「加熱効率」と「強度維持」のためと説明
- 「アコギなことはできない」との発言がさらに消費者の反感を買った
- 消費者庁から直接処分を受けた事実は確認されていない
- 「優良誤認」を疑う消費者の厳しい目は続いている
- 他社(ローソン・ファミマ)は「増量キャンペーン」で支持を集めた
- 対照的に「キッチンDIVE」のデカ盛り弁当が称賛された
- サンドイッチ比較ではセブンは「軽い」が「味は高評価」との情報も
- 2024年5月に就任した阿久津新社長は問題を率直に認めた
- 新社長は「“上げ底弁当”といわれるように、問題はあった」と発言
- 全商品を客目線で見直す「商品総点検」プロジェクトを実施した
- 「日本一クレームが多い」特定の店舗はなく、店舗数の多さが要因か
- 本部社員の離職率は4.5%(2022年度)で特に高くはない
- 新体制の下で消費者の信頼を回復できるかが今後の焦点となる
