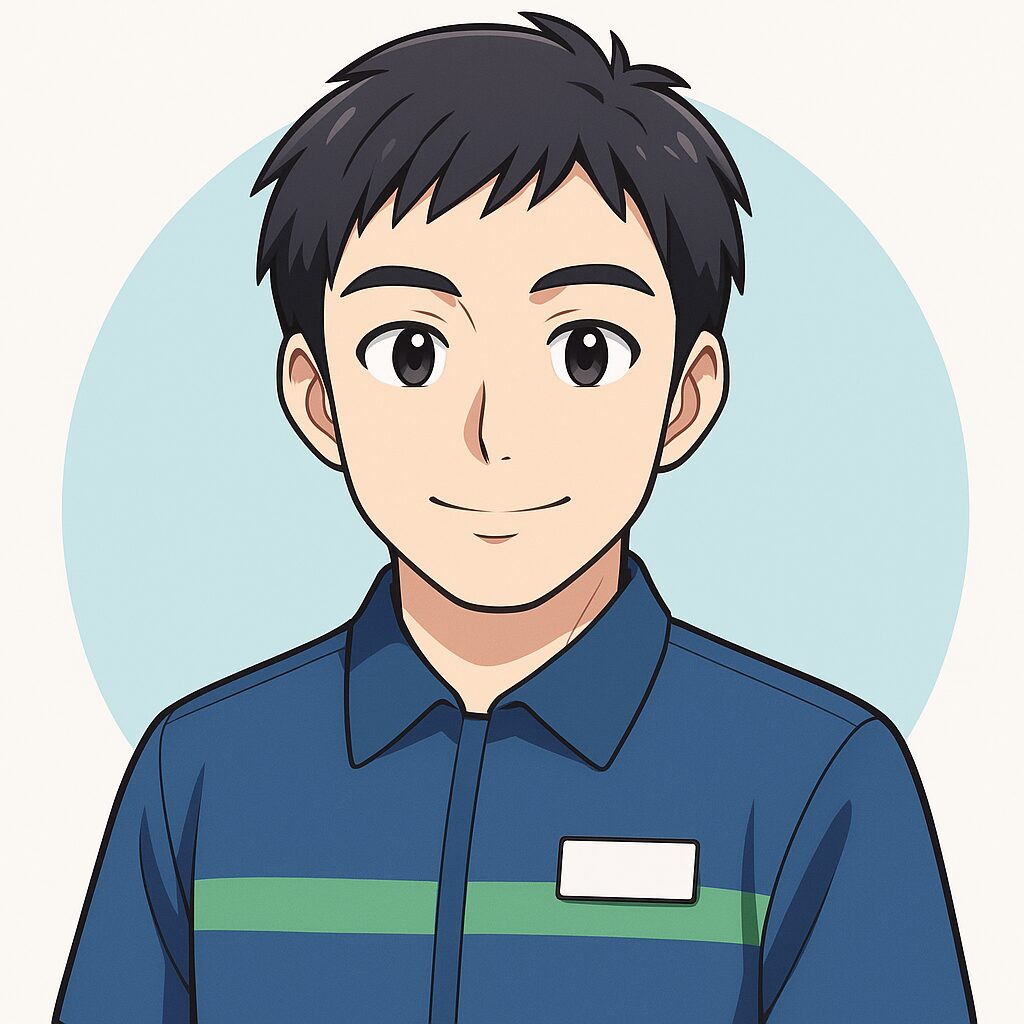マイローカルコンビニ
はじめまして!このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、齋藤 正志と申します。
きっと皆さんは、毎日の食事で手軽なセブンイレブンを利用しながらも、インターネット上で見かける「セブンイレブン 無添加 嘘」という検索ワードを見て、実は体に悪いのではないかと不安を感じているのではないでしょうか。
特に小さなお子様がいるご家庭や健康を意識されている方にとって、おにぎりやパンに含まれる食品添加物の実態や、表示されていない成分の危険性は非常に気になるところだと思います。
私自身も店長になる前は、裏側のラベルを見ても何が本当なのか分からず、ただ漠然とした怖さを抱えていた一人です。ネット上には極端な意見も多いですが、現場で商品を見続けてきた私だからこそお伝えできる、建前ではないリアルな情報を共有させていただきます。
記事のポイント
- ネット上の「嘘」という噂が生まれた法的な背景と構造がわかる
- 表示義務がない「キャリーオーバー」や「加工助剤」の正体を理解できる
- セブンイレブンと他社の添加物に対する戦略の違いが明確になる
- 今日から使える正しい原材料ラベルの読み方が身につく
セブンイレブンの無添加は嘘?誤解の理由

マイローカルコンビニ
なぜ、日本最大手のコンビニであるセブンイレブンに対して「嘘」というショッキングな言葉が投げかけられているのでしょうか。それは、企業が悪意を持って隠蔽しているからではなく、日本の複雑な食品表示法と、消費者が抱く「無添加」へのクリーンなイメージとの間に、埋めがたい深い溝があるからです。
ここでは、その誤解の根本にある法的な仕組みと、私たちが知らされていない表示のルールについて、徹底的に掘り下げて解説していきます。
- 消費者庁ガイドラインと罰則の真実
- 表示されないキャリーオーバーの仕組み
- 加工助剤とは?表示免除の理由
- 原材料ラベルの正しい読み方
- 添加物の安全性と危険性の誤解
消費者庁ガイドラインと罰則の真実
まず最初に、なぜ「嘘」という強い言葉が飛び交っているのか、その根底にあるルールについてお話しさせてください。実は2024年4月から、消費者庁による「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が完全に義務化されたことをご存知でしょうか。これは食品業界にとっては激震とも言える大きなルール変更でした。
これまでは、パッケージの表面に大きく「無添加」とだけ書くことが許されていました。皆さんもスーパーやコンビニで「無添加」と書かれた商品を手に取り、「これは体に良さそうだ」と感じた経験があると思います。しかし、新しいルールではそれが非常に厳しくなりました。
単に「無添加」と書くだけでは、消費者が「保存料も着色料も、化学調味料も、何もかも入っていない」と誤解してしまう恐れがあるからです。実際には保存料は使っていなくても着色料は使っている場合などがあり、これまでの曖昧な表示は消費者を混乱させていました。
なぜセブンは「無添加」と言わなくなったのか
そのため、現在は「具体的に何が無添加なのか(例:保存料不使用)」を明記する必要があります。もし、このガイドラインに違反して消費者に優良誤認(実際よりも著しく優良であると誤解させること)を与えた場合、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令などの重い処分が下される可能性があります。これは企業にとってブランドイメージを損なう致命的なリスクです。
ココがポイント
セブンイレブンがあまり大々的に「無添加」と書かなくなったのは、嘘をついているからではなく、むしろこの厳しいガイドラインを遵守し、法的なリスク(優良誤認)を避けるための誠実な対応とも言えるのです。
また、このガイドラインでは「食品添加物の使用が予期されていない食品への表示」も規制されています。例えば、もともと保存料を使う必要がないミネラルウォーターに「保存料不使用」と書くことは、消費者に「他の水には保存料が入っているのか?」という誤った認識を与えかねないため、不適切とされています。
セブンイレブンが安易に「無添加」を連呼しないのは、こうした細かい規制の一つひとつをクリアし、コンプライアンスを徹底している証拠でもあるのです。(出典:消費者庁『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』)
表示されないキャリーオーバーの仕組み
ここが今回のお話の最大のキモであり、最も多くの消費者が「騙された!」と感じてしまうポイントです。「表示に書いてないのに添加物が入っているなんて、やっぱり嘘じゃないか!」という怒りの声。その原因の正体は、食品表示法で認められた「キャリーオーバー」という特例的な仕組みにあります。
キャリーオーバーとは、一言で言えば「原材料の原材料に含まれる添加物は、最終製品で効果がなければ書かなくていい」というルールです。少し複雑なので、詳しく説明しますね。原材料の製造・加工段階で使用された添加物が、最終的な食品(おにぎりやお弁当など)にも残存していることは珍しくありません。
しかし、その量がごく微量で、最終製品においては保存効果や着色効果などを発揮しない場合、表示を省略しても良いと法律で定められているのです。
おせんべいの例で考えるキャリーオーバー

マイローカルコンビニ
ポイント
例えば、おせんべいの味付けに使われる「醤油」を思い浮かべてください。この醤油自体には、カビを防ぐための「保存料(安息香酸など)」が入っているとします。しかし、その醤油をおせんべいの生地に塗って、高温で焼き上げたとします。すると、最終的に出来上がったおせんべいの中には、醤油由来の保存料がごくわずかに残っているかもしれません。
しかし、その量はあまりに微量で、おせんべい自体を腐らせないようにする効果(保存力)はもうありません。この場合、おせんべいのパッケージの原材料名欄には「醤油」とだけ書けばよく、「保存料」と書く必要はないのです。
これをコンビニの食品に当てはめてみましょう。例えばお弁当の卵焼きや具材なども、製造工程が複雑化しており、セブンイレブンの卵がやばい!偽物説の真実と美味しさの秘密でも触れていますが、加工された卵液を使用する場合があります。これらの原材料段階で使われた添加物が、最終製品であるお弁当には表示されないケースがあります。
セブンイレブンのお弁当やお惣菜も、醤油やソース、具材など多くの複雑な「原材料」を組み合わせて作られています。消費者は「ラベルに書いていない=添加物はゼロ」だと期待して購入します。しかし実際には、原材料の奥深くに潜むキャリーオーバーが存在する可能性があり、「無添加だと思って買ったのに、厳密にはゼロではなかった」というギャップが生まれます。
これが「嘘」と言われる大きな要因になっていますが、法的には完全に合法であり、意図的な隠蔽ではないという点は理解しておく必要があります。
加工助剤とは?表示免除の理由
キャリーオーバーと並んで、消費者の誤解を生みやすいもう一つの大きな要素が「加工助剤」です。これも食品表示法において、堂々と表示が免除される添加物の一つですが、その実態はあまり知られていません。
加工助剤とは、食品を作るプロセス(加工工程)の中では確かに使用されるけれど、最終的に商品として包装される前には除去されたり、中和されたり、あるいは成分が変化して残らないもののことを指します。つまり、「工場のラインでは使っているけれど、皆さんが口にする時にはもういない(あるいは無視できるレベル)」という扱いの添加物です。
野菜サラダのシャキシャキ感の裏側

マイローカルコンビニ
代表的な例としては、カット野菜やサラダを作る際に使用される「次亜塩素酸ナトリウム」などの殺菌料が挙げられます。これはプールの消毒などにも使われる成分ですが、野菜を洗浄して食中毒菌を殺菌するために使われます
。その後、大量の水で十分にすすぎ洗いを行い、成分を洗い流します。そのため、最終的なサラダには成分が残存しない(またはごく微量である)と見なされ、表示には記載されません。
なぜ表示しないのか?
「洗剤のようなもので洗っているのに書かないなんて!」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、これは衛生管理上、O-157などの恐ろしい食中毒を防ぐために非常に重要な工程でもあります。もし殺菌工程を省けば、コンビニのサラダはもっと早く傷み、健康被害のリスクが高まるでしょう。
食品衛生法などの法律に基づいて適切に管理されており、最終製品には影響を与えないレベルになっているため、表示義務がないのです。
例えば、人気商品である野菜スティックの製造においても、徹底した洗浄が行われています。家庭で再現しようとすると難しいあの食感や衛生管理については、セブンイレブン野菜スティックソース完全再現!余った活用法もという記事でも、家庭で楽しむ方法とあわせて紹介していますが、工場の衛生基準は家庭とは比べ物にならないほど厳格なのです。
他にも、みかんの缶詰を作る際に薄皮を溶かすための酸やアルカリ、油脂を抽出するための溶剤なども加工助剤に含まれます。これらは製造効率を高めたり、品質を安定させたりするために不可欠な「黒子」のような存在です。セブンイレブンに限らず、加工食品全般においてこの加工助剤は広く使われていますが、ラベルには一切出てこないため、消費者がその存在を知る由もありません。
「書いてないのに使っている」という事実は、真実を知った時に「騙された」という感情に繋がりやすいのですが、それは現代の食品加工技術と安全管理のトレードオフであることを理解する必要があります。
原材料ラベルの正しい読み方
ここまで、表示されない添加物の話をしてきましたが、それでも私たちが商品を選ぶ際の最大の判断材料はパッケージの表示です。では、私たちはどのようにラベルを見れば良いのでしょうか。私がお店でお客様におすすめしているチェック方法は、表面の「無添加」というキャッチコピーを見るのではなく、裏面の「原材料名」をしっかり見ることです。
特に注目してほしいのが、原材料名の欄にある「/(スラッシュ)」、または改行によって区切られた部分です。現在の食品表示法では、原材料と添加物を明確に区分して記載することが義務付けられており、一般的に「/」の後ろに食品添加物をまとめて記載するルールになっています(改行して別枠に記載する場合もあります)。

マイローカルコンビニ
一括表示の読み解き方
| 表示場所 | 区分 | 記載内容の例 | ポイント |
|---|---|---|---|
| スラッシュの前 | 食品原材料 | うるち米、小麦粉、海苔、塩、豚肉、醤油、砂糖など | 重量の多い順に記載されています。まずはここを見て、メインの食材を確認しましょう。 |
| スラッシュの後 | 食品添加物 | pH調整剤、グリシン、加工澱粉、増粘多糖類、香料、着色料など | ここもしっかり重量順です。何種類くらい書かれているか、パッと見の多さをチェックします。 |
さらに詳しく見るならば、「物質名表示」と「用途名併記」の違いも知っておくと便利です。例えば、「ビタミンC」とだけ書かれていれば物質名ですが、「酸化防止剤(ビタミンC)」と書かれていれば、それが何のために使われているか(用途)も分かります。保存料、甘味料、着色料、酸化防止剤などは、用途名も一緒に書くことが義務付けられています。
パンの表示に関しても同様です。セブンイレブンのパンは添加物が少ないと言われていますが、実際にはどうなのか、セブンイレブンの無添加パン徹底調査!店長が語る自主基準の秘密で詳しく分析しています。「嘘」かどうかを疑うよりも、このスラッシュ以降に何が書かれているか、あるいは書かれていないかを確認することが、自分自身で納得して商品を選ぶ第一歩になります。
セブンイレブンの商品も、このルールに則って正直に記載されています。
添加物の安全性と危険性の誤解
「添加物=悪、危険」「食べ続けると病気になる」というイメージが先行しがちですが、コンビニ店長の立場として、また一人の消費者として冷静に見ていく必要があります。インターネットや週刊誌では、添加物の危険性を煽る記事が人気を集めますが、その多くは科学的な根拠が乏しかったり、極端に大量摂取した場合の実験データを引用していたりします。
日本で使用が認められている食品添加物は、国(内閣府食品安全委員会)が厳格な安全性試験(動物実験など)を行い、人が一生毎日食べ続けても健康に影響がないと推定される量(ADI:一日摂取許容量)を算出しています。そして、実際の食品に使用される量は、このADIよりもはるかに少ない量(100分の1以下など)になるよう、食品衛生法で使用基準が定められています。
キャリーオーバーや加工助剤も、その安全性が担保されているからこそ、表示免除が認められているという側面があります。
リスクの比較:食中毒 vs 添加物
私たちは「添加物のリスク」ばかりに目を向けがちですが、添加物を使わないことによる「食中毒のリスク」については忘れがちです。特にコンビニのお弁当やおにぎりは、製造からお客様の口に入るまで一定の時間がかかります。もし保存効果のある添加物を一切使わなければ、夏場などはあっという間に菌が繁殖し、食中毒事故に繋がるでしょう。
食中毒は、最悪の場合命に関わる即効性のあるリスクです。
また、よくある誤解として「コンビニのお米は危険な添加物まみれだ」という噂がありますが、これについてもセブンイレブンの米は危険?噂の真相と安全性を徹底解説の記事で、工場での炊飯プロセスや使用されている植物油脂の安全性について詳しく解説しています。
ココに注意
もちろん、アレルギーをお持ちの方や、特定の成分に体質的に敏感な方は注意が必要です。表示をよく確認し、自分に合わないものを避けることは重要です。しかし、ネット上の「コンビニ弁当を豚に与えたら奇形が生まれた」といった都市伝説レベルの情報を鵜呑みにして、過度に怖がりすぎる必要はありません。
正しい知識を持ち、リスクとベネフィットのバランスを考えることが大切です。
セブンイレブンの無添加が嘘と言われる背景
法的な仕組みは理解できても、やはり「セブンイレブン 無添加 嘘」という検索が止まないのには、より具体的な商品や企業の姿勢に対する不信感があるからでしょう。ここからは、主力商品である「おにぎり」の原材料や、競合他社との戦略の違い、そしてセブンイレブン独自の取り組みに焦点を当て、なぜ誤解が生まれ続けるのか、その背景を深掘りしていきます。
- おにぎりに使われる調味酢の正体
- 弁当やパンの品質管理と保存料
- ファミマやローソンとの戦略比較
- セブン独自の自主基準と削減努力
- 美味しさと保存性のための必要性
おにぎりに使われる調味酢の正体
セブンイレブンのおにぎり、特にシンプルな「塩むすび」のラベルを裏返して見たことはありますか?そこには、よく「調味酢」という表記があります。実はこれこそが、「無添加の嘘」とネット上で検索される一因になっている可能性が高いのです。
一般的に「酢」と聞くと、家庭にある米酢や穀物酢のような、酸っぱくて健康的な調味料を想像しますよね。「お酢を使っているなら安心だ」と思うのが普通の感覚です。しかし、コンビニのおにぎりに使われている「調味酢」は、単なるお酢とは少し役割が異なります。
これは、ご飯のふっくらとした食感を長時間維持したり、pH(酸性度)を微調整して雑菌の繁殖を抑えたりするための、機能性を持った複合原材料なのです。
「隠された添加物」という感覚の正体

マイローカルコンビニ
この「調味酢」の中身こそがポイントです。メーカーによっては、この調味酢の中に、pH調整剤やグリシンといった添加物が配合されている場合があります。
しかし、食品表示法のルール上、複合原材料として仕入れた場合、その内訳が表示されず、最終製品のラベルには単に「調味酢」とだけ記載されるケース(または調味酢の構成要素としてキャリーオーバー扱いになるケース)があり得ます。
より詳細な成分分析や、実際に使われている添加物の種類については、セブンイレブン無添加おにぎりの真実!現役店長が成分を徹底解説で深掘りしていますので、気になる方はぜひ参考にしてください。
つまり、消費者は「お酢しか入っていないシンプルな塩むすび」だと思って購入しますが、実際には日持ちをさせるための技術的な成分が含まれている可能性があるのです。ここに消費者の抱く「家庭の手作りおにぎり」のイメージと、工場で大量生産される「工業製品としてのおにぎり」の実態とのズレが生じています。
これが「隠された添加物」として認識され、「嘘」という強い反発を生む土壌になっています。
弁当やパンの品質管理と保存料
「コンビニのパンやお弁当は腐らないから怖い」という都市伝説は、未だに根強く残っています。確かに、セブンイレブンのパンやお弁当は、家庭で作ったものよりも日持ちがします。これを見て「大量の保存料(ソルビン酸など)が入っているからだ!」と疑う人が多いのですが、実は近年の実態は少し違います。
最近のセブンイレブンの方針として、昔ながらの強力な「保存料(ソルビン酸、安息香酸など)」は、フレッシュフード(お弁当、おにぎり、サンドイッチなど)においては極力使わない方針をとっています。実際にラベルを見ても、保存料の文字を見かけることは少なくなりました。
腐らない本当の理由
では、なぜ腐らないのでしょうか?魔法ではありません。そこには別の技術と添加物が使われているからです。
一つは、先ほども登場した「pH調整剤」や「グリシン(アミノ酸の一種)」、「酢酸ナトリウム」などの、保存料とは分類されないけれど静菌効果(菌が増えるのを抑える効果)を持つ添加物の併用です。これらを組み合わせることで、保存料という名称を使わずに日持ちを向上させています。
もう一つは、徹底した温度管理(コールドチェーン)と製造環境の衛生管理です。工場内はクリーンルーム化され、製造から配送、店舗に並ぶまで一定の低温(チルド帯や定温)で管理されています。菌を付けない、増やさない環境作りが徹底されているのです。
つまり、「保存料を使っていない」というのは嘘ではありません。しかし、保存料の代わりに別の添加物や技術を使っているため、消費者が期待する「完全な無添加(何も入っていない)」とは異なり、それが「言葉のあやだ」「騙された」という感覚に繋がっているのかもしれません。
お弁当選びに迷った際は、セブンイレブンの弁当と麺のおすすめ紹介も参考に、品質と味のバランスが良いものを選んでみてください。
ファミマやローソンとの戦略比較
競合他社とのコミュニケーション戦略の違いも、セブンイレブンが相対的に誤解を受けやすい理由の一つです。特にファミリーマートの戦略との対比は興味深いものがあります。
コンビニ各社のスタンスの違い
- ファミリーマート:おむすびなどで「保存料・合成着色料・甘味料不使用」と具体的に宣言する戦略をとっています。これは消費者庁のガイドラインにも適合しやすく、消費者に対して「何を避けているか」が明確で、安心感を与えやすい手法です。
- ローソン:「マチの健康ステーション」を掲げ、ナチュロー(ナチュラルローソン)などのブランドを通じて、健康志向や自然派のイメージを醸成しています。全体的に柔らかいイメージ戦略が得意です。
- セブンイレブン:「近くて便利」「美味しさ」を最優先とし、添加物に関しては「必要最低限の使用」という真面目な方針を貫いています。「〇〇不使用」をあまり前面に出さず、あくまで「安全で美味しいものを提供する」という全体最適のスタンスです。
ファミリーマートのように「これを使ってません!」と言い切る方が、消費者としては分かりやすく、「良いことをしている」と感じやすいですよね。一方でセブンイレブンは、内部では厳しい自主基準で管理しているものの、それをアピールするよりも味の追求を優先しているように見えます。
この「沈黙」や「分かりにくさ」が、外から見たときに不透明さに映り、「何か隠しているのではないか?」という疑念を増幅させ、「嘘」という検索行動に繋がっていると考えられます。
一方で、セブンイレブンにも健康を意識したラインナップは存在します。セブンイレブンたんぱく質が摂れるシリーズ徹底解説!活用法もで紹介しているような、栄養成分に配慮した商品は、添加物を気にする層にも一定の評価を得ています。
セブン独自の自主基準と削減努力
あまり一般には知られていませんが、セブンイレブンには法的基準よりもさらに厳しい「食品添加物自主基準」が存在します。私は店長研修などでこの話を聞いた時、その細かさに驚きました。
セブンイレブン・ジャパンは、公式の方針として「お客様の関心の高い添加物は極力控える」としています。具体的には以下のような取り組みがあります。
- 指定添加物の着色料:タール系色素などの指定添加物に該当する着色料の使用を厳しく制限しています。
- リン酸塩の不使用:ハムやソーセージなどの加工肉で結着剤として使われる「リン酸塩」を、オリジナル商品のサンドイッチなどから排除する取り組みを行っています。リン酸塩は過剰摂取するとカルシウムの吸収を阻害すると言われており、健康意識の高い層が気にする成分です。
- 甘味料の制限:人工甘味料の使用も、必要な商品以外では控える傾向にあります。
彼らは「法的に使えるから使う」のではなく、「お客様が嫌がるものは、技術的に可能なら減らす」という姿勢を持っています。特に、プレミアムラインである「金のシリーズ」などは、素材本来の味を追求するため、添加物の使用を極限まで抑えています。
そのこだわりについては、セブンイレブン「金のシリーズ」一覧と人気品の記事をご覧いただくと、その品質の高さがわかるかと思います。
ただ、セブンイレブンのジレンマは、これらの努力を声高に叫びすぎると、「じゃあ他の商品はどうなんだ?」というブーメランになりかねないことや、「美味しさ」という一番の価値がブレてしまうことを恐れているのかもしれません。この地道な「引き算の努力」が消費者に十分に伝わっていないのが現状です。
美味しさと保存性のための必要性
私たち現場の人間からすると、食品添加物は「悪」というだけでなく、「食品ロスを防ぐ」「食中毒を防ぐ」「全国どこでも同じ味を提供する」ための必要悪、あるいは現代社会のインフラという側面も強く感じます。
セブンイレブンは全国に2万店以上の店舗があり、毎日膨大な数のお弁当やおにぎりを供給しています。もし全ての添加物を完全に排除し、家庭と同じ作り方をしてしまったらどうなるでしょうか?おにぎりのご飯は数時間でパサパサになり、味は劣化し、食中毒のリスクは跳ね上がります。
結果として、賞味期限を極端に短くせざるを得ず、大量の売れ残り(食品ロス)が発生し、価格も今の倍以上になるかもしれません。
セブンイレブンが目指しているのは、「家庭の味」と「流通に耐えうる品質」のギリギリのバランス地点です。添加物を使うことで、時間が経っても美味しいご飯を維持し、安全に食べられる状態を保っています。
時にはセブンイレブン詐欺商品まとめ!底上げや空洞の真実のように、容器の形状などで批判を受けることもありますが、品質保持とコスト、そして見栄えのバランスを取る中での企業努力の一環(時に行き過ぎることもありますが)とも言えるでしょう。
よくある質問
Q:セブンイレブンの「無添加」は本当に嘘なのでしょうか?
A:悪意のある嘘ではありません。2024年のガイドライン厳格化に伴い、誤解を招く「無添加」表示を控えているためです。消費者が期待する「完全ゼロ」と、法律で認められた「表示免除(キャリーオーバー等)」のギャップが、「嘘」という噂の原因となっています。
Q:ラベルに書かれていない添加物が入っているのは本当ですか?
A:はい、法的に表示が免除される「キャリーオーバー」や「加工助剤」が含まれる可能性があります。これらは原材料由来の微量な成分や、製造過程で除去されるもので、最終製品に効果を及ぼさないため表示義務がありません。
Q:なぜ他社のように「保存料不使用」と大きく宣伝しないのですか?
A:消費者庁のガイドラインを遵守し、優良誤認などの法的リスクを避けるためです。セブンイレブンは「不使用」を強調するよりも、独自の自主基準で「必要最低限の使用」に留めるという、コンプライアンス重視の戦略をとっています。
Q:お弁当が腐らないのは、危険な保存料が入っているからですか?
A:いいえ、強力な保存料の使用は極力控えています。その代わり、徹底した温度管理(コールドチェーン)、無菌に近い製造環境、そしてpH調整剤などの静菌技術を組み合わせることで、安全に日持ちさせています。
セブンイレブンの無添加は嘘ではない結論

マイローカルコンビニ
ここまで見てきたように、「セブンイレブン 無 添加 嘘」という検索キーワードに対する答えは、「企業が意図的に嘘をついているわけではないが、消費者の期待する『完全無添加(ゼロ添加)』と、企業が提供する『実質的な無添加(表示免除含む)』の間にはギャップがある」というのが真実です。
セブンイレブンは法律を遵守し、表示義務のあるものは記載し、自主基準で減らす努力もしています。決して毒を盛っているわけでも、違法な隠蔽をしているわけでもありません。しかし、キャリーオーバーや加工助剤などの「見えない添加物」の存在や、他社のような分かりやすい「不使用宣言」がないことが、消費者の不安や疑念を生み、「嘘」という言葉に変換されています。
私からのアドバイス
「嘘だ」と感情的に拒絶するのではなく、まずは原材料ラベルを裏返して見てください。「スラッシュの後ろに何が書かれているか」を確認し、自分が許容できる範囲の商品を選ぶこと。そして、コンビニ食だけに頼らず、バランスの良い食事を心がけること。これが、情報過多な現代において、コンビニと賢く付き合うための唯一の方法だと、私は考えています。
健康的な食生活を送るためには、コンビニ商品とうまく付き合うことが大切です。例えば、セブンイレブンでダイエット!1週間の神献立と痩せる組み合わせで提案しているような、栄養バランスを考えた組み合わせを取り入れるのも一つの手です。正しい知識を持って、自分の体と相談しながら商品を選んでいきましょう。