
マイローカルコンビニ
はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、齋藤 正志(さいとう まさし)と申します。
「セブンイレブン どこの国」と検索されたということは、日本で一番よく見かけるコンビニ、セブンイレブンが、本当はどこの国の企業なのか、ふと気になったんだと思います。
私もこの仕事に就く前は、漠然と「アメリカの会社が日本に来たのかな?」なんて思っていました。ですが、セブンイレブンの発祥はアメリカだけど親会社は日本だ、とか、じゃあ韓国のセブンイレブンはどうなの?とか、本社は結局どこにあるのか、知恵袋などの質問サイトでも色々な議論があって、実はちょっと複雑なんですよね。
この記事では、そんなセブンイレブンに関する疑問をスッキリ解決できるよう、セブンイレブンは結局どこの国の企業なのか、また競合のローソンやファミリーマートはどこの国なのかも比較しながら、現役店長の視点から分かりやすくまとめてみました。
記事のポイント
- セブンイレブンの発祥国と現在の親会社がどこか
- 日本とアメリカの資本関係が逆転した歴史
- 日本、アメリカ、韓国など世界の店舗展開
- ローソンやファミマなど他のコンビニとの違い
セブンイレブンはどこの国?結論を解説

マイローカルコンビニ
まずは「セブンイレブン どこの国?」というメインの疑問について、その結論からズバリお答えしていこうと思います。この疑問、実は「〇〇国です」と一言で片付けられない、セブンイレブンの歴史そのものに関わる面白いポイントが隠されているんです。
質問サイト(知恵袋)での議論/疑問
ネットの質問サイト、特にYahoo!知恵袋なんかを覗いてみると、定期的に「セブンイレブンってアメリカ発祥なのに、なんで日本の会社って言われるの?」「結局どっちが本当なの?」といった書き込みを見かけますよね。
この疑問が頻繁に登場すること自体が、セブンイレブンのアイデンティティがいかに多層的かを示している、と私は思います。
多くの人が混乱してしまう主な理由は、二つの側面を混同しやすいからなんです。
- 発祥した国(生まれた国):ブランドが誕生した場所
- 今、所有している国(親会社):現在の経営権を持っている場所
セブンイレブンの場合、この二つが異なる国(アメリカと日本)であり、さらに歴史の途中でその力関係が逆転するという、セブンイレブンの由来に関する噂以上にドラマチックな経緯があるため、「どこの国の企業?」というシンプルな問いが、一筋縄ではいかない議論になりがちなんだと思います。
豆知識:名前の由来は?
ちなみに、「セブン-イレブン」という名前の由来は、ご存知の方も多いかもしれませんが、発祥国のアメリカでのエピソードに基づいています。
1946年、まだ24時間営業が一般的でなかった時代に、お客様の利便性を考えて営業時間を「朝7時(Seven)から夜11時(Eleven)まで」に延長したことが、そのままブランド名になりました。今では24時間営業が当たり前のようになりましたが、当時はこの営業時間の長さ自体が、画期的な「コンビニエンス(便利)」の象徴だったんですね。
どこの国の企業?日本かアメリカか
では、核心の「日本なのかアメリカなのか、どこの国の企業なのか」という点ですね。これに対する最も正確な答えは、以下のようになります。
「発祥はアメリカ合衆国、だけど現在の親会社(所有者)は日本」
これが、現役店長の私から見ても一番しっくりくる回答です。
もう少し具体的に言うと、「セブンイレブン」というコンビニのビジネスモデルやブランドを世界で最初に作ったのはアメリカの会社です。しかし、今やそのグローバルブランドと世界中の店舗網を法的に所有し、経営戦略を決定しているのは日本の企業、という状態なんです。
理解のポイント
セブンイレブンを理解するには、単一の国で見るのではなく、「アメリカで生まれ、日本企業によって買収・再構築され、日本式の経営ノウハウで世界展開するグローバル企業」と捉えるのが、最も実態に近いかなと思います。この「日本企業による再構築」が、おにぎりの品質など、商品力の根幹を支えているとも言えます。
発祥国(どこで生まれたか)は米国
セブンイレブンの歴史は、今から約100年近く前、1927年のアメリカ合衆国テキサス州ダラスで産声を上げました。
驚くかもしれませんが、最初はコンビニではなく、「サウスランド・アイス社」という、文字通り「氷」を売る小売販売店だったんです。1920年代はまだ家庭用冷蔵庫が普及する前で、食品を冷やすための「氷」は、今でいう電気やガスのような生活必需品でした。
この氷屋さんが、ある時、お客様の「氷を買いに来たついでに、他のものも買えたら便利なのに」というニーズに応える形で、パン、牛乳、卵といった日用品も一緒に店頭に置き始めたそうです。これが、今私たちが知る「コンビニエンスストア」の原型、その第一歩とされています。
氷屋さんから始まった「ちょっとした便利」を提供するお店が、のちに世界最大のチェーンストアになるとは、当時は誰も想像しなかったでしょうね。
日本のセブンイレブン一号店の歴史

マイローカルコンビニ
そんなアメリカ生まれのセブンイレブンが、太平洋を渡って日本にやってきたのは、1970年代のことです。
当時、日本でスーパーマーケット「イトーヨーカ堂」を運営していた創業者の鈴木敏文氏(当時)が、アメリカで急速に成長していたセブンイレブンのビジネスモデルに着目しました。
そして1973年、イトーヨーカ堂が、当時の米国の親会社であるサウスランド・コーポレーションとフランチャイズ契約を締結。日本でセブンイレブンを展開する権利を得たのが始まりでした。
そして記念すべき日本のセブン‐イレブン国内第1号店がオープンしたのは、1974年(昭和49年)5月15日のこと。場所は東京都江東区の「豊洲店」です。
この1号店は、元々「山本茂商店」という酒屋さんを改装した店舗だったそうで、アメリカ本部のマニュアルに半信半疑ながらも、日本流の試行錯誤を始めたのが、日本のコンビニ文化の幕開けとなりました。ここから、あのおにぎりやお弁当、さらには今や定番のたまごサンドといった、日本独自のコンビニ文化が花開いていくんですね。
現在のセブンイレブンはどこの国の傘下か
発祥はアメリカ、日本1号店は1974年。ここまでは「アメリカのブランドを日本が借りてきた」という、よくあるフランチャイズの形ですよね。ですが、ここからがセブンイレブンの歴史の面白いところです。どうやって「日本の会社」という側面が強くなっていったのか、現在の資本関係やグローバルな展開について、もう少し詳しく見ていきましょう。
現在の親会社・本社はどこの国か
今現在、日本国内の約2万店以上のセブンイレブンも、発祥国アメリカの約1万2千店以上のセブンイレブンも、そして世界中のセブンイレブンも、すべてを最終的に所有・統括している親会社は、日本の企業です。
その企業の名前は「株式会社セブン&アイ・ホールディングス」。
私たちコンビニ店長にとっては、まさにグループの頂点に立つ会社ですね。セブンイレブンのほか、イトーヨーカドーやデニーズ(日本)、アカチャンホンポなどを傘下に持つ、日本を代表する巨大な小売グループです。(※かつて傘下だったそごう・西武は2023年に売却が完了しました)
つまり、セブンイレブンのグローバルな経営戦略や、ブランドの最終的な意思決定権は、今や日本のセブン&アイ・ホールディングスが握っている、ということになります。(出典:株式会社セブン&アイ・ホールディングス 企業概要)
セブン&アイ・ホールディングスの本社所在地
親会社が日本の企業であるため、当然ながらその本社も日本にあります。
株式会社セブン&アイ・ホールディングスの本社所在地は、東京都千代田区二番町です。
ちなみに、私たち日本のセブンイレブン事業を直接統括している「株式会社セブン‐イレブン・ジャパン」も、同じビルに本社を構えています。一方で、アメリカのセブンイレブン事業を統括する「7-Eleven, Inc.」は、発祥の地であるテキサス州アーヴィングに本社を置いており、日本のセブン‐イレブン・ジャパンの完全子会社として運営されています。
アメリカのセブンイレブンは日本の子会社か
はい、これこそが最大のポイントですが、その通りなんです。今や、発祥国であるアメリカのセブンイレブン(7-Eleven, Inc.)は、日本のセブン&アイ・ホールディングスの完全子会社、もっと言えば日本のセブン‐イレブン・ジャパンの傘下にある企業となっています。
「教えてもらう立場」だった日本が、どうして「教える立場」どころか「親会社」になれたのか。ここには「資本の逆転劇」と呼べるドラマがありました。
資本の逆転劇:本家アメリカの経営危機

マイローカルコンビニ
1980年代後半から1990年代にかけ、なんと、発祥国であるアメリカの親会社(当時のサウスランド社)が、多角化の失敗や放漫経営などで経営危機に陥ってしまったんです。一方で、日本のセブンイレブンは、独自に開発した緻密な商品管理(POSシステム)や、高品質なお弁当・おにぎり、革新的な物流網を武器に、急成長を遂げていました。
日本による救済と買収
本家の経営危機に際し、1991年、日本のフランチャイズ運営会社だったイトーヨーカ堂(とセブン‐イレブン・ジャパン)が、米国サウスランド社の株式の過半数(約70%)を取得し、経営支援に乗り出しました。この時点で、事実上の親子関係が逆転したんです。
その後、2005年にイトーヨーカ堂グループが持株会社制に移行し、「株式会社セブン&アイ・ホールディングス」が設立されると同時に、残っていた米国7-Eleven, Inc.の株式もすべて取得し、完全に子会社化しました。
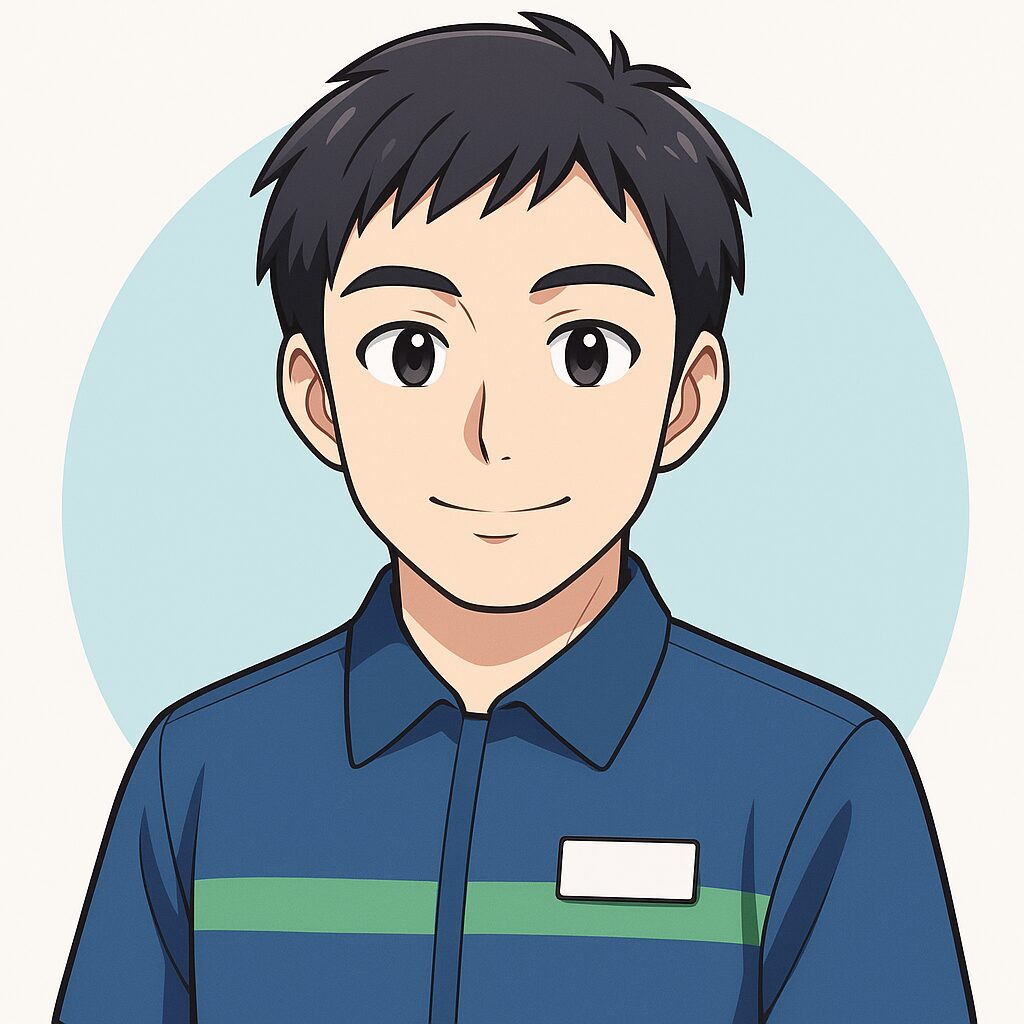
世界の店舗数と展開国

マイローカルコンビニ
日本のノウハウと資本によって再構築されたセブンイレブンは、今や世界最大のコンビニチェーンとなり、2024年の時点では世界20以上の国と地域で、合計85,000店以上も展開しているそうです。私のお店もその8万5千分の1だと思うと、本当にすごいスケールですよね…。
この膨大な店舗網が、どの国に集中しているのか。店舗数の国別ランキングを見てみると、セブンイレブンの「今」の中心地がどこなのか、ハッキリと分かります。
| 順位 | 国・地域 | 店舗数(概算) |
|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 約21,500店 |
| 2位 | 韓国 | 約13,100店 |
| 3位 | アメリカ | 約12,600店 |
| 4位 | 台湾 | 約6,800店 |
| 5位 | 中国 | 約5,000店 |
こうして客観的なデータで見ると、一目瞭然ですよね。発祥国のアメリカ(3位)を大きく引き離して、日本(1位)が単独で世界最多の店舗数を誇っています。さらに驚くべきは、2位の韓国、4位の台湾と、トップ5のうち4つまでがアジアの国・地域で占められていることです。
この事実は、セブンイレブンという業態が、元々のアメリカ型よりも、日本で進化を遂げた「高密度・高付加価値型」のモデル(高品質な食品、カップデリに代表されるきめ細かなサービス)の方が、現代のアジアの都市型ライフスタイルに完璧にマッチしたことを示している、と私は思います。公共料金の支払いや宅配便の受付など、生活インフラとしての役割も大きいですよね。
海外(特に韓国・アメリカ)のセブンイレブン

マイローカルコンビニ
同じ「セブンイレブン」の緑と赤の看板を掲げていても、国によって売っているものやお店の雰囲気がかなり違います。これも海外旅行の密かな楽しみだったりしますよね。
アメリカのセブンイレブン
発祥国のアメリカは、今でも店舗数は多いですが、日本とは少し業態が異なります。主力商品は何と言っても「スラーピー(フローズンドリンク)」や「ビッグガルフ(日本では考えられない超特大サイズのドリンク)」といった大容量の飲料や、スナック菓子、ホットドッグなどです。
また、広大な国土と車社会を反映して、ガソリンスタンドに併設されている店舗が非常に多いのも特徴です。日本のように、お弁当やおにぎり、高品質なチルド惣菜がビシッと棚に並んでいる、というきめ細かさよりは、ドライブのついでに「サッと寄って、サッと買う」というスタイルが主流ですね。日本のように店内で作るスムージーが全店にある、という状況とは少し異なります。
韓国のセブンイレブン
お隣の韓国は、今や日本に次ぐ世界第2位の「コンビニ大国」です。日本と同様に、ソウルなどの都市部には「一歩歩けばコンビニに当たる」と言われるほど高密度に出店しています。
日本のセブンイレブンのノウハウをベースに、キンパ(韓国風海苔巻き)やトッポギ、独自開発のインスタントラーメンなど、韓国ならではの即食商品が充実しています。
ライバルチェーンとの競争も日本以上に激しく、常に新しいサービスや商品が生まれている、非常にダイナミックな市場ですね。(日本でもアイドルコラボなどが時々話題になりますが、韓国もそうしたキャンペーンが多い印象です)
日本モデルの世界展開
最近では、親会社であるセブン&アイHDが、日本で大成功した「高品質な食品(お弁当や総菜、おにぎり)の開発・管理ノウハウ」を、アメリカの店舗にも本格的に導入しようと力を入れているそうです。
これは「プレイブック」戦略と呼ばれていて、日本の緻密なオペレーションをアメリカに移植する試みです。将的には、アメリカのセブンイレブンでも、日本のような高品質なソフトクリームが当たり前に買える日が来るかもしれませんね。
競合コンビニ(ローソン・ファミマ)の発祥国
「セブンイレブンの歴史は分かったけど、じゃあ、いつも利用してるローソンやファミマはどこの国なの?」と気になる方もいるかもしれませんね。日本のコンビニ大手3社で、発祥国を比べてみましょう。
ローソン(LAWSON)
まず、青い看板のローソン。実はローソンも、セブンイレブンと同じくアメリカ発祥なんです。ちょっと意外ですよね。
元々は1939年に、オハイオ州のJ.J.ローソン氏という人物が始めた牛乳販売店、通称「ローソンさんの牛乳屋さん」がルーツです。この牛乳屋さんの看板が、今もロゴマークに残っています。日本では1975年にダイエーが提携して1号店をオープンさせました。現在は三菱商事の連結子会社となっていますね。
ファミリーマート(FamilyMart)
次に、緑と青のラインが特徴のファミリーマート。こちらは、純粋な日本発祥のコンビニエンスストアです。
元々はスーパーの西友ストア(当時は西友グループ)のコンビニエンスストア事業部として、1973年に埼玉県で1号店がオープンしました。(セブンの1号店より少し早いんですね)ちなみにセブンイレブンでは専用の紅茶マシンを置いている店舗もありますが、こうした独自サービスも各社で競い合っています。
大手3社の発祥国まとめ

マイローカルコンビニ
- セブンイレブン:アメリカ発祥(現在は日本資本)
- ローソン:アメリカ発祥(現在は日本資本)
- ファミリーマート:日本発祥(純国産)
こうして並べてみると、今や日本の生活に欠かせない大手コンビニ3社のうち、セブンとローソンはアメリカ発祥、ファミマだけが日本発祥、ということになります。日本のコンビニ文化は、アメリカのビジネスモデルを日本流に徹底的に改良・進化させることで花開いた、と言えそうですね。最近では一番くじなどのエンタメ企画も、その進化の一つかもしれません。
よくある質問
Q:セブンイレブンは結局、どこの国の企業なのですか?
A:最も正確な答えは「発祥はアメリカ、しかし現在の親会社(所有者)は日本」となります。1927年にアメリカ・テキサス州で氷販売店として生まれましたが、現在は日本の「株式会社セブン&アイ・ホールディングス」がグローバルな経営権を持つ親会社です。
Q:では、アメリカのセブンイレブンも日本の会社なのですか?
A:はい、その通りです。1990年代にアメリカの本家が経営危機に陥った際、当時フランチャイズ契約だった日本のイトーヨーカ堂が経営支援を行い、最終的に買収しました。現在、アメリカの「7-Eleven, Inc.」は、日本のセブン‐イレブン・ジャパンの完全子会社となっています。
Q:世界で一番セブンイレブンが多い国はどこですか?
A:発祥国のアメリカ(3位)ではなく、日本が約21,500店で世界1位です。2位は韓国、4位は台湾となっており、日本で進化した経営ノウハウがアジア市場で広く受け入れられ、店舗網が集中しています。
Q:ローソンやファミリーマートはどこの国で発祥しましたか?
A:ローソンもセブンイレブンと同じくアメリカ発祥です(現在は日本資本)。ファミリーマートは純粋な日本発祥のコンビニエンスストアです。
セブンイレブンはどこの国なのか総括
さて、ここまでセブンイレブンの発祥から現在までの長い道のりを、駆け足で見てきました。「セブンイレブン どこの国」かという、シンプルながら奥深いこの問いに対して、私なりの最終的な回答をまとめさせていただきますね。
セブンイレブンの「国籍」への3つの答え
セブンイレブンの真のアイデンティティは、以下の3つの側面で理解するのが最も正確だと、私は思います。
- 歴史的な発祥国(生まれた場所)は「アメリカ」(1927年、テキサス州の氷屋)
- 現在の資本的支配(所有者)は「日本」(セブン&アイHDの完全子会社)
- 経営ノウハウと市場の中心地は「日本・アジア」(店舗数1位は日本、日本式モデルが世界標準)
つまり、セブンイレブンは「アメリカで生まれ、日本資本によって買収・再構築され、日本式の経営哲学によって世界最大の小売ネットワークを運営しているグローバル企業」である、と定義するのが一番しっくりくるかなと思います。
アメリカで生まれた「便利さの種」が、日本という土壌で「高品質・高密度」という独自の花を咲かせ、今やその花(ノウハウ)が世界中に輸出されている…。セブンイレブンの歴史は、単なるコンビニという枠を超えた、グローバルビジネスのダイナミックな事例なんですね。
私もいち店長として、時には本社へのクレームなど、厳しいご意見をいただくこともありますが、日々進化するセブンイレブンの一員であることに、ちょっとした誇りを感じながら、毎日お店に立っています。
免責事項
本記事で紹介した店舗数、歴史、資本関係などのデータは、執筆時点(2025年11月)で入手可能な公開情報や一般的な情報、および概算に基づいています。店舗数は日々変動しており、企業戦略も常に更新されています。
最新の正確な企業情報、財務情報(IR)、およびグローバル戦略に関する詳細については、必ず株式会社セブン&アイ・ホールディングスの公式サイトにて、一次情報をご確認いただくようお願いいたします。
