
マイローカルコンビニ
はじめまして! このブログ「マイローカルコンビニ」の運営責任者であり、現役のコンビニ店長を務めております、**齋藤 正志(さいとう まさし)**と申します。
セブンイレブンでこれからアルバイトを始めようとしている方や、研修が始まったばかりの方にとって、一番の不安は「レジ操作」じゃないかなと思います。私もコンビニのレジを外から見ているだけでも、機能が多すぎて覚えるのが大変そうだと感じます。本当に複雑そうですよね。
「セブンイレブン レジ 画面 店員 側」と検索している方は、きっと具体的な操作マニュアルや画面の見方について、詳細な情報を探しているんですよね。特に、公共料金や税金の支払い(セブンイレブン レジ 収納代行)は、お金のミスが許されないので一番緊張する業務かもしれません。
最近ではみそきんの再販などでレジに行列ができることもあり、プレッシャーは大きいですよね。PayPayなどのバーコード決済の押し方ひとつとっても、種類が多くて戸惑うこともあるでしょう。
また、たばこを売る時の年齢確認ボタンを押すタイミングや、研修で習う操作マニュアルだけでは分かりにくい部分、そして「なぜ毎回押すんだろう?」と疑問に思うかもしれない、あの独特な客層キー入力の必要性など、具体的な疑問や不安がたくさんあるかなと思います。
この記事では、セブンイレブンのレジが「どういう仕組みで動いているのか」「なぜそのボタンがそこにあるのか」という設計思想のレベルから、店員さん側の視点でできるだけわかりやすく、深く掘り下げて解説していきます。単なる操作方法だけでなく、その「理由」を理解すれば、きっと不安も軽くなり、自信を持って操作できるようになるはずです。
記事のポイント
- レジを構成する3つの主要な機器とそれぞれの具体的な役割
- 商品スキャンから会計完了、客層キー入力までの基本的な操作フロー詳細
- 公共料金やバーコード決済時の画面の切り替わり方
- 操作ミスをシステムが防いでくれる仕組み
セブンイレブンのレジ画面の店員側の基本操作

マイローカルコンビニ
まずは基本操作からですね。セブンイレブンのレジは一見するとボタンやメニューが多くて圧倒されるかもしれませんが、店員側の画面やキーボードの配置には、すべてちゃんと「理由」があるんです。ここでは、研修で最初に学ぶ、基本的な機器の役割と、最も頻繁に行う商品販売の流れを詳しく見ていきましょう。
レジ研修で覚える3つの機器
まず、私たちが「レジ」と呼んでいるものは、実際には主に3つの機器が連携して動いている一つの「ワークステーション(業務端末)」と考えた方が分かりやすいかもしれません。2017年頃から導入された第7次POSレジスターがこれにあたるようです。
- メインPOSレジスター(本体)
店員さんがメインで操作する、キーボードと画面がついた機械です。調査によると東芝テック製が全国の店舗に納入されているようですね。ここで商品のバーコード情報を処理したり、お預かり金額を入力したり、決済方法を選んだりします。
高速なCPUと大容量メモリを搭載し、スピーディな処理と障害の予兆管理まで行う、まさにレジシステムの中核です。店員さんが直接触れる、最も重要なインターフェースですね。 - お客様側ディスプレイ(大型液晶)
お客さん側に向いている15インチほどの大きな画面です。これは単なる金額表示機ではありません。文字サイズを大きくして視認性を高め、購入金額の表示はもちろん、新商品やキャンペーンの告知、nanacoの残高表示など、「おもてなし端末」としての役割も担っています。お客さんの買い忘れを防いだり、次の購入を促したりする機能も持っているわけです。
- 決済端末(カード・電子マネー用)
クレジットカードや電子マネー、非接触IC決済を処理するための専用端末です。パナソニック製の「JT-R610CR」などが使われているようです。これが非常に重要で、店員さんの責任範囲を大きく変えました。
高セキュリティ化と店員の負荷軽減
この決済端末は、国際的なセキュリティ基準である「PCI PTS SRED」要件に対応しています。これは、カード情報を読み取った瞬間にデータを暗号化して転送する技術で、情報漏えいのリスクを極限まで小さくするものです。(出典:PCI Security Standards Council)
これにより、従来は店員側で行っていたICカードの挿入口や暗証番号(PIN)入力パッドが、お客様側に設置されました。お客様がご自身でカード挿入・暗証番号入力・タップ決済を完結できるようになったのです。
結果として、店員さんはお客様のクレジットカードや暗証番号に一切触れる必要がなくなったのです。これは、オペレーションの負荷軽減だけでなく、「不正利用を疑われるかも」といった心理的負担を大幅に減らす、とても大きな進歩と言えますね。
研修では、これら3つがセットで「レジ」であり、それぞれが「情報処理」「情報伝達」「決済処理」と役割分担して動いている、と覚えるのが良さそうです。
操作マニュアル:基本の流れ
一番基本となる、おにぎりや飲料、雑誌などを販売する時のオペレーションフローです。この一連の流れの中に、POSシステムの設計思想が凝縮されています。
商品販売の基本5ステップ
- 商品スキャン: ハンドスキャナーで商品のバーコードを読み取ります。スキャンと同時に、店員側・お客様側の両方の画面に商品名と価格が即時表示されます。POSシステムが自動的に価格を記録・計算するため、手打ちによる入力ミスや計算ミスといったヒューマンエラーを防止できます。これは、「ぷらいち」のような「1つ買うともう1つもらえる」キャンペーンや、「15%引き」のシールが貼られた商品の割引計算なども、自動で正確に行ってくれます。
- 【重要】年齢確認(該当商品のみ): タバコやお酒など、法律で年齢確認が義務付けられている商品のバーコードをスキャンした場合、レジの挙動が変化します。(詳細は次項で詳述)
- 会計(決済方法の選択): お客さんに「お支払い方法はいかがなさいますか?」と伺い、レジ画面(主に液晶キー)に表示されている該当の決済ボタンを押します。
- 会計完了: 決済が完了すると、高速サーマルプリンタからレシートが印刷されます。商品とレシート(領収書)をお客様にお渡しします。
- 【重要】客層キー押下: 会計完了後、または次のお客様の商品をスキャンするまでの間に、物理ボタンである「客層キー」を押します。
この流れがすべての基本ですね。特に、「スキャンさえすれば、複雑な割引計算も自動でやってくれる」という信頼感が、店員さんのレジ操作における精神的な負担を大きく減らしてくれていると思います。
ハードキーと液晶画面の役割
セブンイレブンの現行レジ(第7次POSレジスター)が非常に興味深いのは、昔ながらの物理ボタン(ハードキー)と、スマートフォンのようなタッチパネル(液晶キーボード)が両方搭載されている「ハイブリッド設計」を採用している点です。
これは、コンビニ特有の「会計スピード」と「サービスの多様化」という、時に相反する要求を両立させるための、非常に合理的な設計思想に基づいていると私は考えています。
液晶キーボード(タッチパネル)の役割
こちらは「柔軟性」と「拡張性」を担当しています。コンビニの業務は、新しいサービスが次々と追加されていくのが特徴です。
- 新しいバーコード決済(〇〇ペイ)の導入
- 外国人従業員向けの多言語対応(画面の言語切替え)
- 宅配便の受付など、操作手順が複雑なサービス業務
- イラストによる操作ガイダンスの表示
このように、将来的に変更・追加される可能性が高い機能や、マニュアル無しでも直感的に操作できるよう誘導が必要な複雑な操作は、すべて液晶画面側が担当しています。これにより、システムのカスタマイズが容易になっているんですね。新しいキャンペーンが始まっても、物理キーを交換する必要がなく、ソフトウェアの更新だけで対応できます。
ハードウェアキー(物理ボタン)の役割
一方で、あえて「変わらない」物理ボタンとして残されているキーもあります。こちらは「速度」と「確実性」を担当しています。
- 客層キー(性別・年齢層)
- 数字を入力するテンキー(お預かり金額の入力など)
- 「現金」や「小計」など、使用頻度が極めて高いキー
これらのキーは、毎日何百回、何千回と押されることが前提です。コンビニのレジは1秒でも早くお客さんをさばく「速度」が命。その点で、液晶画面を「見て・触る」よりも、手元を見ずに打てる「物理キー」の方が圧倒的に速いんです。
また、客層キーのように「絶対に操作をスキップしてほしくない」重要なキーでもあります。これらを液晶画面の奥の階層に置いてしまうと、操作効率が著しく低下したり、操作忘れが発生したりします。
だからこそ、ブラインドタッチ(手元を見ずに)できるほどの確実性と速度が求められるキーは、あえて押し心地のある物理ボタンとして、一番操作しやすい場所に残されているんですね。
店員さんは、新しく複雑な操作(例:サービス受付)は「画面(液晶)」を見ながら慎重に行い、日常的な操作(例:客層入力)は「物理キー」で素早く行うよう、システムによって自然に誘導されるわけです。
年齢確認ボタンと画面ロック
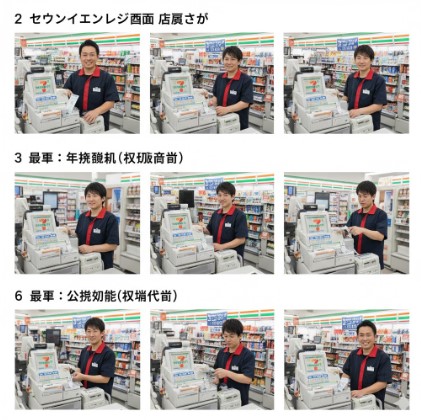
マイローカルコンビニ
新人アルバイトさんが研修で最初に「おっ」と緊張するのが、たぶんこの機能じゃないでしょうか。タバコやお酒(チューハイやハイボールなど)など、法律(未成年者喫煙禁止法・未成年者飲酒禁止法)で年齢確認が義務付けられている商品をスキャンした時の動作です。
これらの商品のバーコードをスキャンした瞬間、レジの画面は一時的にロック状態(他の操作を一切受け付けない状態)になります。そして、画面の中央には「【年齢確認】お客様は20歳以上ですか?」といった趣旨の確認ダイアログが強制的に表示されます。
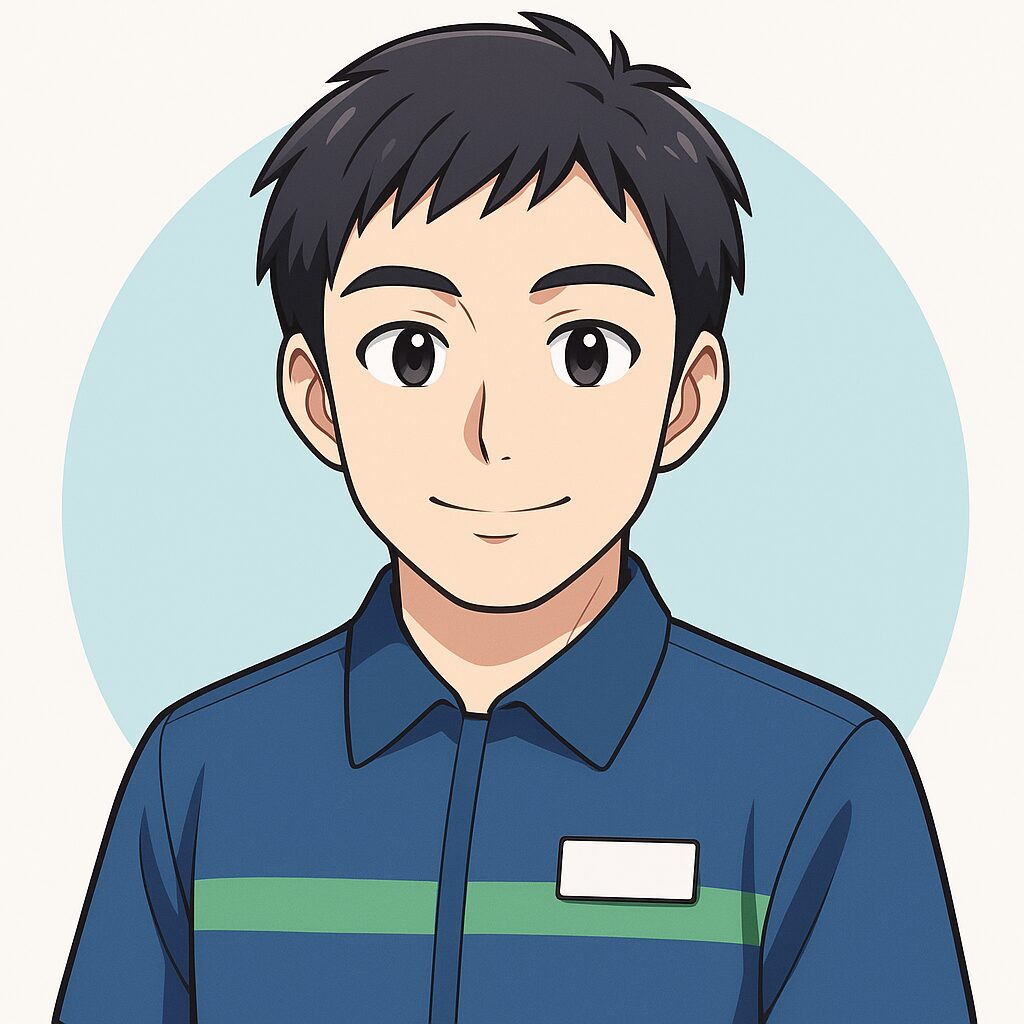
これは、店員さんの「うっかりミス」や「忙しくて確認を忘れた」といった事態をシステムレベルで徹底的に防止するための「フェイルセーフ(失敗防止)」機能です。万が一の法律違反を犯さないよう、店員個人ではなく、システムが強力にサポートしてくれる。むしろ新人さんにとっては、これほど安心できる機能もないとも言えそうですね。
客層キー入力は重要な業務

マイローカルコンビニ
会計が終わった後(または次のお客様の商品をスキャンする前)に押す「客層キー」。レジの物理キーの一番手前、押しやすいところに配置されている、性別(男女)と年齢層(10代、20代、30代…など)が描かれたボタン群ですね。これ、何のためにあるかご存知ですか?
これは、店員さんが目で見て判断したお客さんの「性別」と「推定される年齢層」を入力するための専用キーです。
なぜ客層キーが「物理キー」として存在するのか?
セブンイレブンは、競合他社(ローソンやファミリーマート)と比較して、独自のポイントカード(nanacoを除く共通ポイントなど)の利用率が低い傾向にあると指摘されています。つまり、PontaカードやTカードのように「会員情報(年齢・性別)」と「購買情報」を自動で紐付けられる機会が相対的に少ない、という特性があると考えられます。
一方で、コンビニ経営の根幹は、「いつ・何が・どのように売れたか」というPOSデータを分析することにあります。セブンイレブンにとって、この「誰が(どの層が)買ったか」という客層データは、「何が売れたか」という商品データと同等に重要な経営指標なんです。
もしこの客層入力が「液晶画面の奥の階層」にあると、どうなるでしょうか? おそらく、お昼のピーク時など多忙な時間帯に、店員さんが操作をスキップしてしまう可能性が非常に高くなります。
だからこそ、あえて押しやすい「物理キー」としてレジスターの最も操作しやすい場所(一等地)に配置することで、操作の確実性を高め、データ収集率を最大化しているわけです。
この地道なデータが、「30代男性にはこのにんにく黒胡椒餃子が売れている」「20代女性はシャインマスカットのパフェをこの時間に買う」といった分析を可能にし、商品の納品時間や品揃えの最適化に繋がっているのです。
これは、セブンイレブンの精緻なデータドリブン経営と仮説検証を支える、店員さんの非常に重要な「業務」の一つなのです。
忙しい時につい押し忘れてしまうこともあるかもしれませんが、このボタン一つ一つが明日の商品発注や、もしかしたら次のカレーフェスの商品開発に繋がっていると思うと、少し見方が変わるかもしれませんね。
セブンイレブンのレジ画面の店員側の応用操作
基本がわかったら、次は応用操作です。ここが新人さんの不安がピークに達する場所かもしれませんね。特に公共料金の支払い(収納代行)や、種類が多すぎるバーコード決済など、お金の扱いや覚えることが多い操作について、セブンイレブンのレジ画面が店員側をどう賢くサポートしてくれるのかを、さらに詳しく見ていきます。
最重要:公共料金(収納代行)

マイローカルコンビニ
電気、ガス、水道などの公共料金、住民税や自動車税などの税金、各種通販サイトのコンビニ支払いなど、「払込票」を処理する業務です。これは、私が思うに、レジ業務の中で最もリスクが高く、絶対にミスが許されない業務です。
最大のミス:「もらい忘れ」と「空打ち」
収納代行で一番怖いのが、お客さんからお金をもらう前に「支払い完了」の操作をしてしまう(通称「空打ち」とも言われるようです)ことです。もし、お客さんが「あ、お金が足りなかった」と店を出てしまい、そのまま戻らなかったら、レジの現金とシステム上の売上に差異(不足)が生じます。
この不足分は、万が一の場合、従業員自身の給与から差し引かれるといった重大な事態に発展する可能性も指摘されており(店舗のルールによりますが)、絶対に避けなければなりません。
操作は、お客さんから「払込票(バーコードが印刷された紙)」、または「払込票番号(スマホ画面やメモ)」を受け取るところから始まります。店員さんは、そのバーコードをスキャンするか、番号をレジに入力します。
収納代行の鉄則:「先お預かり」
この業務のミスを防ぐ、たった一つの、しかし最も重要な原則が「先お預かり」です。バーコードをスキャンしたら、まず「〇〇円、先にお預かりします」とハッキリお客様に伝え、現金(またはnanaco)を先に受け取ります。
受け取った金額をしっかり確認し、レジに投入(またはnanacoをタッチしてもらう準備)ができてから、初めて「支払い完了」のボタンを押す。この手順を徹底することが、自分自身を守る最大の防御策になります。
収納代行とnanaco決済
払込票のバーコードをスキャン(または番号を入力)した瞬間、レジ画面の「モード」が強制的に切り替わります。これが、セブンイレブンのレジが店員さんを守る、最大にして最強の機能だと私は思います。
ご存知の通り、収納代行の支払いは、原則として「現金」または「nanaco(電子マネー)」のみと厳格に決められています。(一部、nanacoも不可の払込票があります)
なぜクレジットカードや他の決済がダメなのか? それは、収納代行が「代金を収納して、その情報を企業に送る」という仲介業務だからです。
もしクレジットカードで支払われ、後で「チャージバック(支払い拒否)」が発生すると、お店が代金を立て替えることになり、非常に複雑な問題になるため、リスク回避の観点から不可とされています。nanacoは事前にお金を入金する「プリペイド(前払い)」なので、現金と同じ扱いというわけですね。
このルールを徹底させるため、払込票をスキャンしてシステムが「あ、これは収納代行だ」と認識した瞬間、レジ画面(液晶)上にある「クレジットカード」「交通系IC(Suicaなど)」「iD」「QUICPay」「バーコード決済(PayPayなど)」といった、規定外の決済ボタンがすべて無効化(グレーアウトして押せない状態)されます。
決済方法の対応マトリクス(簡易版)
| 決済手段 | ① 一般商品 (おにぎり等) | ② 収納代行 (公共料金, 税金) | ③ その他 (金券, チャージ等) |
|---|---|---|---|
| 現金 | ○ | ◎ (推奨) | ◎ (必須) |
| nanaco | ○ | ○ (唯一可能) | × (一部不可) |
| 交通系IC (Suica等) | ○ | × (不可) | × |
| その他電子マネー (iD, Edy等) | ○ | × (不可) | × |
| クレジットカード | ○ | × (不可) | × |
| バーコード決済 (PayPay等) | ○ | × (不可) | × |
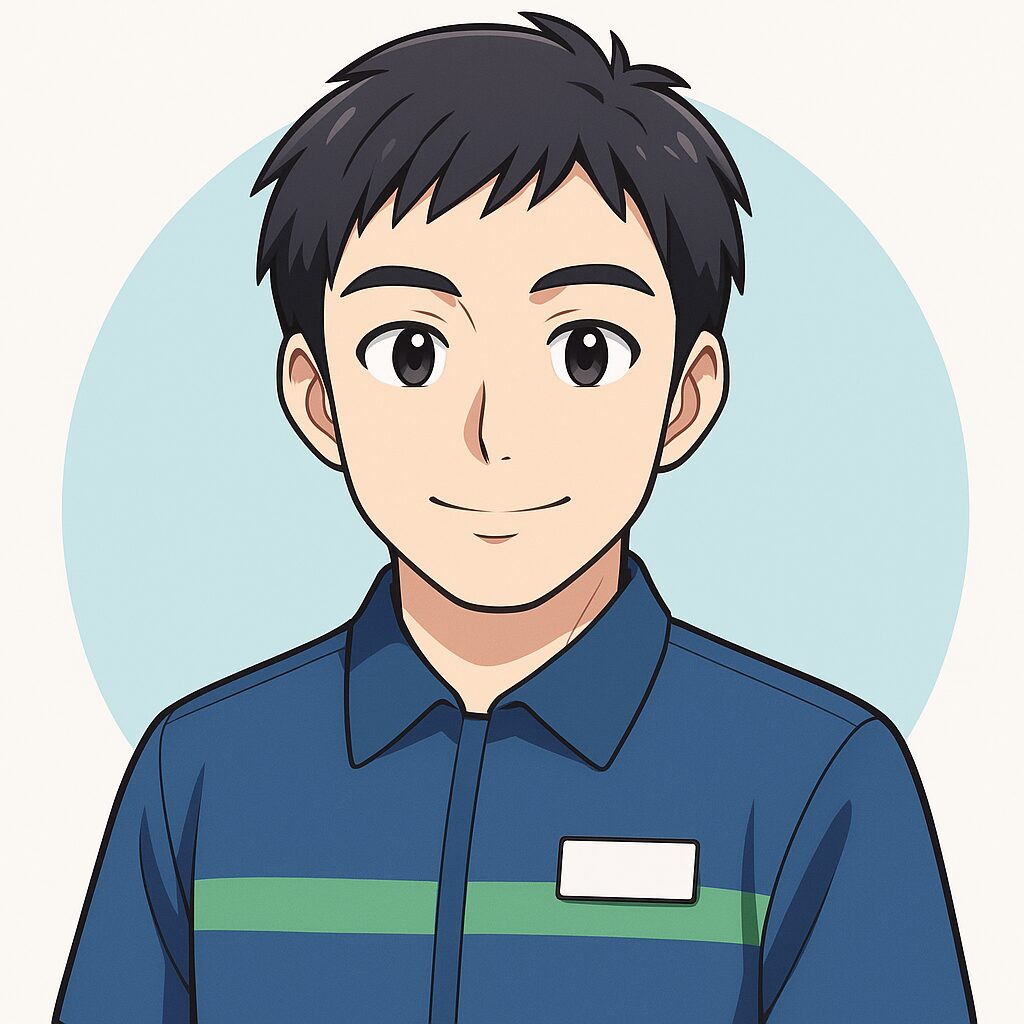
このように、店員さんが物理的に選択できるボタンは、原則として「現金」と「nanaco」の2つだけになります。これは、店員さんが忙しさのあまり、うっかり誤ってルール違反の決済(例:「クレジットカード」ボタンを押してしまう)をしてしまうのを、システムレベルで防止する「ガードレール機能」なんですね。
ですから、店員さんが取るべき行動は決まっています。まず「先お預かりします」と声をかけて現金を受け取り、それを確認してから、押せるようになっている「現金」ボタンを押す。この「先預かり」の徹底が、ミスを防ぐ最大の鍵となります。
バーコード決済ボタンの仕組み

マイローカルコンビニ
次に、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払い、au PAY…など、今や無数にある「バーコード決済」です。お客さんから「〇〇ペイで」と言われた時、研修中の新人さんなら「え、ボタンはどれだっけ?」と焦ってしまうかもしれません。
でも、安心してください。セブンイレブンのレジは、ここでも店員さんの負担を劇的に減らす、非常に優れた工夫がされています。それが「統一ボタン」機能です。
店員さんは「バーコード決済」を押すだけ
お客さんから「PayPayで」や「楽天ペイで」と言われても、店員さんは液晶画面上で「PayPayボタン」や「楽天ペイボタン」を必死に探す必要はありません。
多くの場合、液晶画面にある「バーコード決済」という趣旨の統一ボタンを1回押すだけでOKです。あとは、お客さんが提示したスマートフォンの決済アプリに表示されたバーコード(またはQRコード)を、ハンドスキャナーで読み取るだけです。
スキャンさえすれば、POSシステムが、読み取ったバーコードの情報を解析し、「あ、これはPayPayだな」「これはd払いだな」と自動的に決済事業者を判別して処理を実行してくれるんです。
これは、店員さんの学習コスト(「このロゴはPayPay」「このロゴは楽天ペイ」とすべて覚える手間)と、操作ミス(例:「PayPay」ボタンを押したのに「LINE Pay」をスキャンしてしまう)を劇的に削減するために開発された、ものすごく賢い仕組みだと思います。
この「バーコードをスキャンする」という操作は、セブンイレブンアプリのキャンペーンでクーポンバーコードを読み取る時など、他の操作とも共通しているので、すぐに慣れるかなと思います。
メルカリ(宅配便)の操作
最近は、メルカリなどのフリマアプリで売れた商品を、コンビニから発送するお客さんも非常に多いですよね。この宅配便の受付も、レジの液晶画面(タッチパネル)で行うのが基本です。(この部分は私の調査と推察も含まれます)
おおよその流れは以下のようになるかと思います。
- お客さんから「メルカリ(またはヤマト)の発送をお願いします」と荷物を渡される。
- 店員さんは、液晶画面の「サービスメニュー」や「受付」といったボタンから「宅配便受付(またはメルカリ受付)」の項目を選択する。
- お客さんのスマートフォン(メルカリアプリなど)に表示された、発送用の受付バーコードをハンドスキャナーでスキャンする。
- (推察)POSレジと連動した専用プリンタから、配送伝票(送り状)がシール形式で印刷される。
- (推察)店員さんはその伝票を荷物に貼り付け、メジャー(巻尺)で荷物のサイズ(60サイズ、80サイズなど)を計測し、レジに入力する。
- 会計(運賃の決済)を行う。(※メルカリの場合は、運賃は売上金から引かれるため、その場でのレジ会計は発生しないケースが多いですね。操作としては「受付完了」のような形になると思われます。ヤマトの通常の宅配便の場合は、ここでお客さんから運賃をいただきます。)
これも、液晶画面が「次は何をしてください」「サイズを測ってください」と操作を誘導してくれるはずなので、焦らずに画面の指示に従うことが大切ですね。
チケット発券とマルチコピー機
店内に設置されている多機能なマルチコピー機とも、レジは一部のサービスで密接に連動しています。
レジ操作が「不要」なサービス
「コピー(白黒・カラー)」「写真プリント」「分割プリント」「名刺印刷」「住民票の発行」など、お客さんがマルチコピー機で操作を完結し、その場で料金も支払う(コインベンダー)サービスは、レジ操作は一切不要です。
レジ操作が「必要」なサービス
レジが関係するのは、マルチコピー機で手続きだけ行い、支払いはレジで行うサービスです。
- チケットぴあなどの各種チケット発券(ライブ、レジャー施設、高速バスなど)
- プリペイドカード販売(Amazonギフト券、Apple Gift Cardなど)
- スポーツ振興くじ(toto、BIG)の購入
- 一番くじや特定 のコラボグッズ(パンどろぼうなど)の引換券発券
この場合、お客さんはマルチコピー機で必要な手続きを行い、最後に印刷される「申込券(バーコード付きのレシート)」をレジカウンターに持ってきます。店員さんは、その「申込券」のバーコードをスキャンして会計をします。
これも私の推察ですが、これらの「申込券」は金券(またはそれに準ずる)扱いとなるため、スキャンした瞬間にPOSシステムのモードが切り替わり、決済方法が限定される(例:原則、現金のみ)可能性が極めて高いです。収納代行と同じように、システムがミスを防いでくれる「ガードレール機能」がここでも働くと考えられますね。
返品処理と取消ボタン
最後に、お客さんからのキャンセルや返品の申し出があった場合の操作です。これは、会計「前」と「後」で、操作の難易度と重大性がまったく違ってきます。
会計「前」のキャンセル(1点取消・全取消)
これは比較的簡単です。お客さんが商品をスキャンした後、「あ、やっぱりこのペットボトルコーヒーやめます」と言った時ですね。
- 1点取消(訂正): 会計完了前であれば、液晶画面の「訂正」や「(直前)取消」ボタンを押し、キャンセルしたい商品のバーコードを再度スキャン(またはリストから選択)することで、スキャンした商品のリストから削除できるはずです。
- 全取消(取引中止): 「全部やめます」となった場合は、「取引中止」や「全取消」といったボタンで、その会計自体をリセットします。
会計「後」の「返品」
問題はこちらです。一度会計が完了し、レシートが発行された後の「返品」は、はるかに複雑で厳格な操作となります。
なぜなら、一度成立した売上を取り消し、レジから現金を出す(返金する)という行為は、不正な返金や内部不正のリスクと直結するからです。
そのため、通常とは異なる「サービスメニュー」や、場合によっては店長やマネージャーしか操作できない「責任者モード」のような画面から、レシートに印字されたバーコード(取引番号)をスキャンするなどの厳格な手順が必要となります。
ここでも、「ミスや不正を防ぐために、あえて操作を複雑にしている」というシステムの設計意図が明確に感じられますね。
よくある質問
Q:公共料金(収納代行)の支払いで、クレジットカードやPayPayが使えないのはなぜですか?
A:収納代行は「代金収納」という仲介業務であり、後払い(チャージバックリスク)となるクレジットカードやバーコード決済は利用できません。システムが自動で決済方法を「現金」または前払い式の「nanaco」のみに限定します。
Q:なぜ会計のたびに「客層キー」(性別・年齢ボタン)を押す必要があるのですか?
A:セブンイレブンは他社に比べポイントカード等で得られる客層データが少ないためです。店員が入力するデータは「いつ・何が・どの層に売れたか」を分析する重要な経営指標となり、商品開発や品揃えに活用されています。
Q:PayPayや楽天ペイなど、バーコード決済の種類が多くて覚えるのが不安です。
A:心配ありません。セブンイレブンのレジは「バーコード決済」という統一ボタンを1回押すだけです。その後にお客様のスマホをスキャンすれば、システムが自動で決済会社(PayPay、楽天ペイなど)を判別して処理してくれます。
Q:タバコやお酒の年齢確認を忘れてしまったらどうなりますか?
A:システムがミスを防いでくれます。対象商品をスキャンした瞬間、レジ画面は自動でロックされます。画面中央の「はい(確認しました)」ボタンを押すまで会計が一切進まなくなる「フェイルセーフ機能」が搭載されています。
総括:セブンイレブンのレジ画面店員側の理解が鍵

マイローカルコンビニ
ここまで、セブンイレブンのレジ操作について、基本から応用まで詳しく見てきました。いかがだったでしょうか。
改めて振り返ると、セブンイレブン レジ 画面 店員 側のインターフェースは、単なる「お金を計算する道具」ではなく、店員さんの操作を助け、重大なミスから守り、そして会社の経営を支える重要データを収集するための、非常によく考えられた「賢い司令塔」だということがわかります。
その設計思想は、大きく分けて2つの目的に集約されると私は分析しています。
- 「ガードレール」としての役割 新人スタッフを、金銭授受のミス(収納代行)や決済方法の違反(ルール違反)といった危険なエラーから守ります。収納代行時に決済ボタンを自動的に無効化(グレーアウト)する機能は、その最たる例です。
- 「データ収集メカニズム」としての役割 セブンイレブンのビジネスモデルの根幹である「データ収集」を、現場で確実に実行させます。あえて押しやすい物理キーとして残された「客層キー」は、多忙なピークタイム中でも正確なマーケティングデータを収集するための、強力なメカニズムです。
これからレジに立つあなたは、ただ操作を「暗記」するのではなく、「なぜ、この画面は今こうなっているのか?」「なぜ、このボタンはここにあるのか?」という「理由」を少しだけ意識してみてください。
何をスキャンしたかによって、店員に許される操作を動的に変えてくれる。この「レジの賢さ」を味方につけることこそが、操作への不安を「自信」に変え、正確で迅速なオペレーションを実現するための、最も確実な近道じゃないかなと、私は思います。応援しています!
